「激減した赤トンボ」が見事復活した地域の秘密 自然の恵みを疎かにしないところからの実践
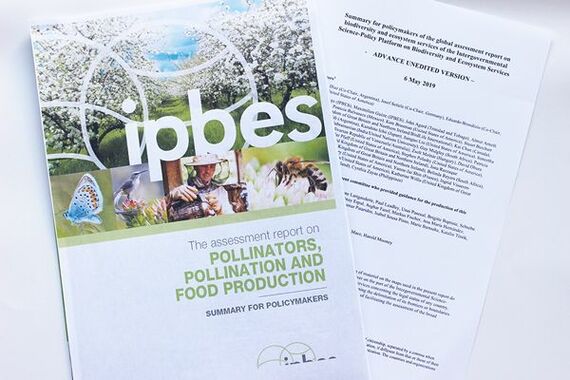
農水省は2017年、前年のIPBESの報告書を受け、農家と養蜂家の間の情報共有を改善し、農薬散布の際にミツバチに農薬がかからないように気をつける、という対応策を打ち出した。しかし、基本的には、①日本と欧州では農薬のタイプや散布の方法が異なる、②養蜂家が飼うミツバチのCCDは、日本では起きていない――とし、厳しい農薬規制には消極的な立場だ。
トンボもミツバチも。身近な生きものをキープする意味
赤トンボの減少をめぐり、研究者らによる調査では農薬以外にさまざまな要因も挙げられた。その1つは圃場整備。全国でため池や水路のコンクリート護岸化や用水路の暗渠化、ため池の埋め立てなどが行われたことで、トンボをはじめ生きものの生息環境が大きく変わった。また、耕作放棄地の増加や、開発による周辺の森林や草地の減少も要因とされる。
ミツバチの場合、アメリカでは、セイヨウミツバチを飼う養蜂家の間から「変だぞ」と声が上がった。しかし、農作物の受粉に活躍しているのは、「管理されたミツバチ」だけではなく、野生のハチ類やそのほかの鳥類を含む「花粉媒介生物」だ。
国立研究開発法人森林研究・整備機構の主任研究員、滝久智さん(43歳)(森林昆虫研究領域)らが茨城県のそば畑で2007~2008年に調査を行った結果、畑から100メートルの範囲内に森林と草地があるかどうか、3キロメートル圏内に森林があるかどうかで、そばの実の付き方に差が出た。
そばは、「他家受粉生物」で、花に来る昆虫の手助けにより受粉する。畑周辺の土地利用の変化が、管理されたミツバチや野生の昆虫の生息や活動に影響し、ひいては収穫量に影響することがわかった。
ミツバチなど花粉媒介生物の働きや価値はなかなか見えにくい。ましてや、受粉に活躍するわけでもない赤トンボをはじめ、田んぼを生活の場とするさまざまな生きものの価値は、見過ごされがちだ。だが、自然の恵みをおろそかにしない、というところから始める実践は、少しずつ広がっている。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら