残業「年1824時間」超えも1割、常軌を逸した病院勤務医の激務っぷり。それでも医師の”働き方改革”が進まない理由とは?安野貴博氏が解説

「医師の働き方改革」という喫緊の課題
まず朝8時に出勤したら、所属する医局の入院患者の健康状態をひと通りチェックしたあと、9時から絶え間なくやってくる外来患者の診察に当たり、急患の対応もするため昼食をとる暇すらない。あっという間に夕方になり、そこからはカルテを書いたり、上司に当たる教授の論文を手伝ったり、研究費獲得のための書類作成などのデスクワーク。夜間は、別の病院の「当直」としてアルバイトに行く。静かな夜を過ごせればラッキーだが、急患の来院に何度も叩き起こされることもよくある。処置を済ませ、朝方に少し仮眠をとってから再び出勤……。
これが日本の大学病院で働く勤務医の、ごく標準的な労働実態です。
時間外労働が年960時間を超えて勤務している病院勤務医は、全体の37.8%。月の労働時間に換算すると約80時間で、いわゆる「過労死ライン」に相当します。全体のなかの上位10%の医師は「年1824時間」を超える時間外労働に従事しており、常軌を逸した激務となっています。
「医師の働き方改革」と高齢化社会のピークを迎える社会の医療体制維持の両立は、都として解決策を示さなくてはならない喫緊の課題です。
2050年に「都民の3人に1人が高齢者」という時代を迎える東京には、限られた医療リソースで、いかに超高齢社会に対応するかという先進的なモデルを示す責務があると考えます。
冒頭の例に戻ると、なぜ医師たちはこれほど大変な思いをしてまで当直のアルバイトに行くのでしょうか。そこには、勤務医としての収入が少なく、大学病院においてはまだ教授にはなれない30~40代の医師は教授の“助手”のような待遇になってしまうという構造的な要因があります。アルバイトのほうが時間単価は圧倒的に高いこと、また人手不足が深刻な地域医療が医師のバイトで支えられている、という事情もあります。

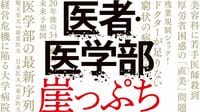





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら