残業「年1824時間」超えも1割、常軌を逸した病院勤務医の激務っぷり。それでも医師の”働き方改革”が進まない理由とは?安野貴博氏が解説
今のテクノロジーが医療の現場で十分に活用されるレベルにまだ達していない面もあります。端的な例でいえば、呼吸が止まって倒れている人が目の前にいるような場面では、心臓マッサージを施すことが最優先です。スマホのアプリを立ち上げている暇なんてありません。緊急性が高い状況のなかでも、医療従事者がほとんど意識することなく使えるテクノロジーをどうつくり込んでいくのか、エンジニアリング側のさらなる努力が必要な部分でしょう。
また、DXは業務効率化に資するといっても、運用上どうしても情報の入力作業が発生します。病院内では情報管理がしっかりされていたのに、退院して介護施設や自宅に移ると、情報管理が脆弱になり、健康状態の推移がわかりにくくなることもよくある話です。
介護の現場でケアマネジャーや訪問ヘルパーの方が、「入所者がどんな食事をとったか」「健康状態はどうだったか」などをシステムに入力することが徹底されれば、提携先の病院においてもデジタル化の恩恵は最大化されますが、それは容易なことではありません。 慢性的に人手が足りず忙しい介護従事者にとって、手間が増える入力のインセンティブが乏しいからです。医療職に向けて提供されているサービスが介護職向けには提供されていないなど、医療と介護を地続きでつなぐプラットフォームが少ないという課題もあります。
これに関していえば、今後生成AIの活用によって、現場で交わされる会話の内容をもとに大部分の情報が自動で入力される支援システムが誕生する可能性は高いと考えます。
医療現場の方は、その内容をチェックして、足りない部分を補うだけでよいということになれば、現場の効率化は大きく進むでしょう。
夜間・休日のオンライン診療のメリット
医療DXによって実現可能な政策の一つが、夜間・休日のオンライン診療の拡充です。
都内では共働きの現役世代が増えています。彼らは平日の日中に病院に行くのが難しく、仮に病院に足を運んだとしても、高齢者を中心とした混雑に巻き込まれて長い待ち時間を強いられることが多々あります。そうした状況を踏まえ、夜間・休日のオンライン診療という形で現役世代の医療アクセスを担保していくことは重要です。不妊治療についても同様で、オンライン化によりアクセシビリティを高めることは少子化対策にもつながります。
まずは夜間診療の現状を確認してみましょう。
救急医療は、患者の重症度や緊急性に応じて、一次救急(入院や手術の必要がなく、自力で受診できる比較的軽症な患者に対応)、二次救急(入院や手術が必要な患者を24時間体制で受け入れる)、三次救急(一次救急や二次救急では対応が難しい、生命に関わる重症患者に対応)の3つに分類され、それぞれ対応する医療機関も異なります。

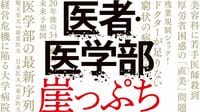





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら