残業「年1824時間」超えも1割、常軌を逸した病院勤務医の激務っぷり。それでも医師の”働き方改革”が進まない理由とは?安野貴博氏が解説
こうした過酷な環境は、当然のように若い世代からは忌避され、近年では多くの医師免許取得者が、収入の高い美容整形の開業医を目指すという流れもできつつあります。
2024年から始まった「医師の働き方改革」の新しい規制で「勤務医の時間外労働の年間上限は原則960時間とする」との規制が設けられましたが、そもそも病院側は、時間外労働も含めたトータルの勤怠管理に消極的です。医師の勤怠状況を把握している都内病院の割合は55.5%に過ぎません(東京都保健医療局「令和4年度医師の働き方改革に係る準備状況調査」)。
また、労働時間を明確に管理することが、患者の命に責任をもつ医師という職業に馴染みにくい面もあります。手術の最中に終業時間が来たからといって、メスを置いて帰るわけにはいきません。
医療の問題は複雑で、例えば厚生労働省の管轄下にある診療報酬の問題など、国政レベルでなければ介入できない要素も多いのが実情ですが、ここでは都政でできるアプローチに絞って論じたいと思います。
医療DXを阻む事情
医療現場の負担軽減のカギとなるのは、DXによる業務の大幅な効率化です。
都内に14ある都立病院において、病院間の連絡には、いまだにファックスが使われているような状況があります。しかも、送信後に「ファックス届きましたか?」と確認の電話を入れるような非効率がまかり通っているほか、縦割りの構造で病院ごとにカルテの様式が異なっていたりもします。
DXにより病院間あるいは介護施設との間の情報連携を簡易化・迅速化すれば、一定の業務効率化が図られるでしょう。
石川県七尾市にある恵寿総合病院が、医療AI事業を展開するUbie株式会社とともに行った、生成AIを活用した実証実験の結果は注目に値します。報告によると、退院サマリ作成時間が生成AIを使用することで42.5%の入力時間減少と、27.2%の心理的負担の低減が認められ、業務負担軽減効果が有意に実証されました。
合わせて、医療機関の職員向けにITリテラシーを高める講座などのサポートを行うのも手です。忙しさのあまり自主的に取り組めるだけの余裕がないのが現状であるため、都から後押しするような援助が有効でしょう。
一方で、医療や介護の世界には、DX化をすれば何でも解決するわけでもない特殊な要因がいくつかあります。
例えば、病院の理事長と地元の政治家が懇意にしているとVIP枠で患者が送られてくる、というようなことがあったりします。そのような患者を現場にいる先生は断りきれないので、すでに病棟は満床でも“隠しベッド”を引っ張り出してきて多少無理してでも受け入れます。その是非はともかく、否が応でもそうした人間関係で左右されるファクターがある世界のため、デジタル化で万事丸く収まるというわけでもないのです。

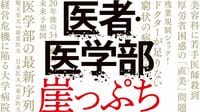





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら