残業「年1824時間」超えも1割、常軌を逸した病院勤務医の激務っぷり。それでも医師の”働き方改革”が進まない理由とは?安野貴博氏が解説
夜間に発症した患者は、一次救急の病院(主に地域の医院やクリニックなど)はほとんど閉まっているため、おのずと二次救急に対応した医療機関を訪れることになります。しかし、実際には軽症の患者も多いのが実情で、救急車を呼んだ人のうち54%が入院の必要のない軽症だったというデータもあるほどです(東京消防庁資料)。それでも、心配ゆえに病院に駆け込む人が絶えないことが、本来は重症者を受け入れるべき二次救急の逼迫につながっています。
オンラインの夜間・休日診療が実現すれば、患者は病院まで足を運ぶことなく医師の診察を受けられることになります。症状を話して、「大丈夫ですよ。朝になってから病院で受診してくださいね」という医師の言葉を聞けるだけで安心できるケースも多くあるといわれ、二次救急の逼迫を緩和する効果が期待できます。
診療のオンライン化は、医師にとっても大きなメリットがあります。仮に病院に当直で出向くとなれば8時間の当直勤務と、往復の移動時間もかかりますが、オンラインであれば自宅からでも対応可能であるため、負担がかなり減るのです。自宅でも対応できるオンライン診察は、医師にとっても歓迎すべきものといえるでしょう。
地域間の繁閑調整にも活用できる
オンラインであれば医師と患者がどこにいるかは問題でなくなるため、仕組み次第で、地域間の繁閑調整にも活用できます。現に、東京都医師会は都道府県を超えたオンライン診療を提供すべきだと提言しています。
2024年9月末、東京都武蔵野市にある吉祥寺南病院が建物の老朽化のため、診療を休止しました。同市の吉祥寺駅周辺では、24時間体制で患者を受け入れる二次救急医療機関が相次いで休止・閉鎖しており、東京都内だけで見ても医療リソースの偏在が顕著になり始めています。オンライン診療が普及すれば、東京都外の閑散期の医師が、アルバイトで診察にあたることも可能になるでしょう。
千葉県野田市では、2024年春から夜間・休日における軽症者向けのオンライン診療がスタートしました。自宅でスマホなどの画面越しに、内科・小児科の医師の診察を受けられ、発熱や咳・のどの痛み、胃痛、頭痛、吐き気などの症状に対応しています。
また那覇市立病院では、2024年11月から小児科のオンライン夜間診療の試験的な運用を開始しました。沖縄県内全域を対象に、平日のみならず、土日祝日の夜間診療にも対応しています。以前は地域の小児科医がローテーションで休日の診療を担当していましたが、あまりに負担が大きかったためオンラインに舵を切った形です。
この医療リソースの逼迫問題にひときわ切実な思いを感じているのは、私自身、救急医療のおかげで命を救われた経験があるからです。12歳のころ、私は急性虫垂炎になって、あと1時間処置が遅れていれば盲腸が破裂して死んでいたかもしれないということがありました。そのときはたまたま千葉の病院が受け入れ先として見つかって、九死に一生を得ました。今全国各地で、救急車を呼んでも救急患者の受け入れ先がすぐに決まらない「搬送が困難な事例」も多く報告されています。
救えるはずの命を救うためにも、救急サービスは重症度や緊急性に応じた適切な利用と、医療の現場を圧迫しない仕組みの構築が早急に求められています。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

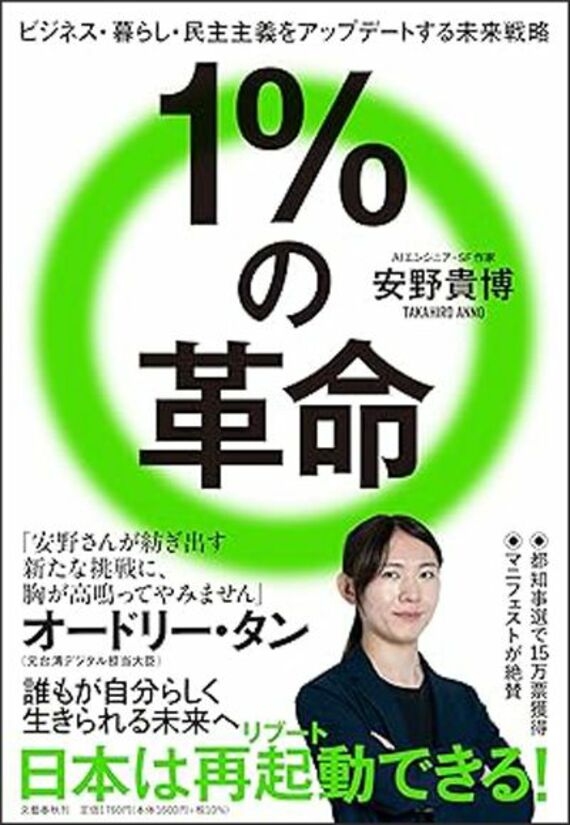
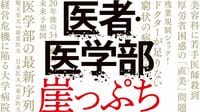





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら