「人間はなぜ働き続けるのか?」休みなくひたすら作業…産業革命で生じた過酷すぎる労働環境
もう1つは、労働者が団結して使用者と団体交渉をし、その際にストライキなどの団体行動を行うことを認める「集団的自由」です。これは、労使間の力関係の格差のなかで事実上自由を奪われていた労働者に対し、集団として自由を行使することを認め、労使間の事実上の力関係の格差を是正しようとするものでした。
工場労働者の声が政党や議会に届くように
このような形で、市民革命がもたらした個人の自由を修正し、労働者に集団的な保護・自由を与える労働法が誕生した背景には、市民革命がもたらしたもう1つの重要な側面である国民主権=民主主義という法原理があったことも、歴史的には大切な点です。
19世紀に産業革命=工業化が進展し、過酷な状況で働いていた工場労働者の数が増加していくなかで、フランスでは1848年、ドイツでは1867年、アメリカでは1870年に、納税額等の制限のない普通選挙制度が導入されました(当時はまだ成人男子に限定されてはいましたが)。
この民主主義の基盤の拡大のなかで、数が増加していた工場労働者の声が政党や議会の場に届くようになり、労働者の置かれた状況を改善する法律(労働法)が制定されるようになったのです。
真 由「労働法って、市民革命がもたらした民主主義を基盤にしながら、市民革命の負の側面を修正していったんですね。歴史って複雑に絡み合ってるんですね」
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

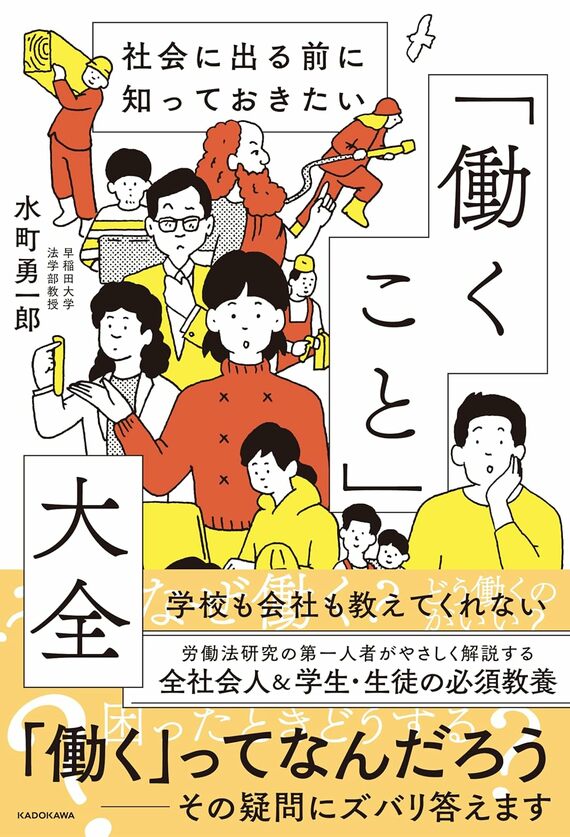






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら