
大衆芸能として愛された「浄瑠璃」
2024年の大河ドラマ「光る君へ」では、「散楽」(さんがく)という伝統芸能がストーリーを展開するうえで、重要な役割を果たした。
まひろ(紫式部)が屋敷の帰りに散楽を観にいくと、そこには、右大臣家の三男・三郎(藤原道長)も訪れており、幼少期に出会っていた2人は再会。物語が動き出すこととなった。
曲芸や幻術、歌舞や音楽、物まねなど、雑多な内容を持つ「散楽」は、奈良時代に中国大陸からもたらされた。次第に日本の芸能と混じり合いながら、滑稽な物まねや寸劇がメインとなっていき、「猿楽(さるがく・さるごう」と呼ばれるようになる。
そして室町時代には、猿楽に歌や舞、そしてリズムを取り入れた「能楽」が、観阿弥・世阿弥親子によって大成していく。能楽は、とりわけ猿楽の滑稽な要素が発達した「狂言」とともに、鎌倉時代から室町時代を経て、江戸時代に至るまで広く行われることになる。
だが、能楽や狂言の鑑賞者は、公卿や武家など上流階級に限られており、奈良・平安時代の散楽のように大衆を楽しませるものではなくなっていた。


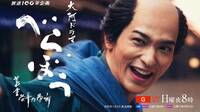






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら