
大切な人を「見送る」ときに考えること
曹洞宗を開いた道元禅師が、こんな言葉を残しています。
「たき木、はひとなる、さらにかへりてたき木となるべきにあらず。しかあるを、灰はのち、薪はさきと見取すべからず。しるべし、薪は薪の法位に住して、さきありのちあり。前後ありといへども、前後際斷せり。灰は灰の法位にありて、のちありさきあり」(「正法眼蔵』の「現成公案」)
ここに「前後際断(ぜんごさいだん)」という言葉があります。
私たちは、薪と灰を見ればつい、薪が前の姿であり、灰は後の姿であるというふうに、薪と灰をひと続きのものとして捉えるのがならいです。
「それではいけない」とするのが道元禅師です。薪は薪として、灰は灰として完結しており、薪と灰は連続していない。つまり前後は断ち切れているのだと道元禅師は説きます。
同じことが、生と死の関係においても言えます。
死は生の後の姿ではなく、死は生の後の姿でもない。生の延長線上に死があるのではなく、生と死は断ち切れています。

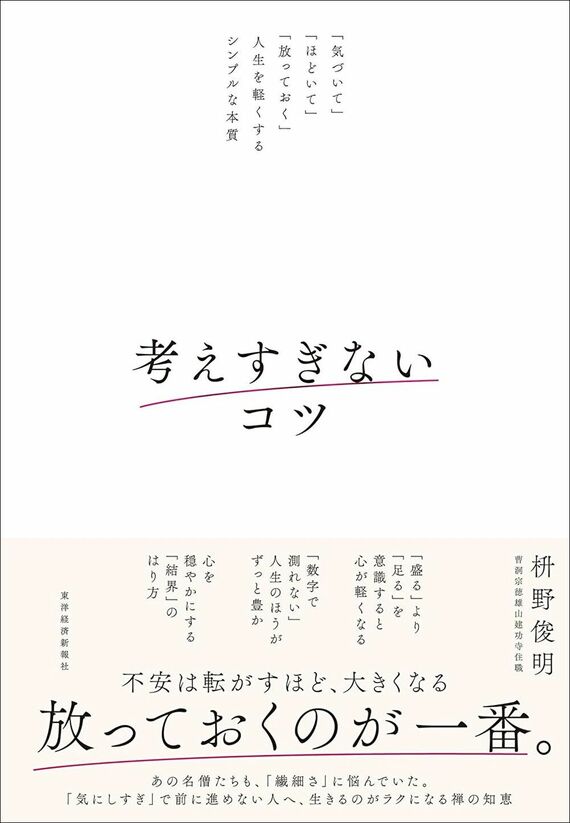






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら