大将はそのまま督の君の父、致仕の大臣の邸に立ち寄った。弟の君たちが大勢やってきている。「こちらにお入りください」と言われ、大将は寝殿の表座敷のほうに入る。大臣は涙を静めてから大将と対面する。いつまでも老いを感じさせない端整な顔立ちがひどく痩せ衰えて、髭なども手入れをしておらず伸び放題で、子が親の喪に服すよりずっと悲しみが深そうである。大将はその姿を見るなりとてもこらえきれなくなり、しかしあまりにも止めどなく涙を流すのも見苦しいと思い、なんとかして隠している。大臣も、この大将は息子ととくべつに仲がよかったのだと思って見ると、涙が雨のように降り落ち続けて、止めることができず、尽きることのない悲しい胸の内を互いに語り合う。
一条の邸を訪問したことなどを大将は話す。いっそう激しく、春雨かと思えるほど、軒の雫(しずく)と変わらないほどさらに涙で袖を濡らしている。御息所が詠んだ「柳の芽にぞ」という歌を、畳紙(たとうがみ)に書き留めておいたものを渡すと、「目も見えないほどだ」と大臣は涙を絞るようにして見ている。泣き顔で見入っている様は、いつもの気強くきっぱりした、自信満々の様子はみじんもなく、みっともない。実際はそうすぐれた歌というわけでもないのだが、この「玉はぬく(露の玉を貫くように)」というところが、まったくその通りだと思うと心が乱れて、長いこと涙をこらえきれなくなる。
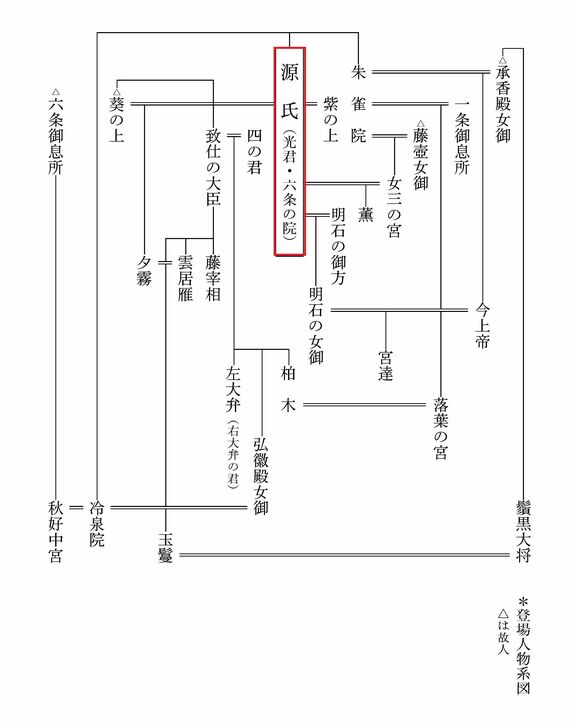
放心したように空を仰ぐ
「あなたの母君(葵の上)が亡くなった秋は、もうこれ以上悲しいことはないと思ったものですが、女性(にょしょう)の場合はそういう決まりがあるために、人前に出ることもまれですし、日頃のあれこれが表に出ることはありませんから、悲しみも内々のものでした。ところが、息子はふつつか者ではありましたが、帝もお見捨てにならず、ようやく一人前になって、官位ものぼるにつれて頼りとする人々もおのずと数多くなりました。亡くなったことを驚き、残念がる者もあちこちにいるようです。しかし私のこの深い悲しみは、そうした世間一般の人望とか、官位などとは関係なく、ただ、とくに人と変わるところがあったわけではない、息子本人の有様だけが、たまらなく恋しいのです。いったいどうしたらこの悲しみが忘れられるでしょう」と、放心したように空を仰ぐ。
夕暮れの雲は鈍色(にびいろ)に霞んでいる。花の散ってしまった枝々を、大臣は今日はじめて目に留める。先ほどの畳紙に、
木(こ)の下(した)の雫(しづく)に濡れてさかさまに霞(かすみ)の衣(ころも)着たる春かな
(子に先立たれた悲しみの涙に濡れて、逆さまに、親のほうが喪服を着ている春となってしまった)
大将の君、
亡き人も思はざりけむうち捨てて夕べの霞君着たれとは
(亡くなった人も思いも寄らなかったことでしょう、あなたさまを残して、喪服を着せることとなるとは)
弟である右大弁の君、
うらめしや霞の衣(ころも)誰(たれ)着よと春よりさきに花の散りけむ
(恨めしいことです。だれに喪服を着せようと思って、春が逝(ゆ)くよりも先に花は散ってしまったのでしょう)
督の君の法要は、世間に例のないほど盛大に執り行う。督の君の異母妹である、大将の妻(雲居雁)はもちろんのこと、大将自身も誦経なども格別に心をこめて、深い配慮のもとに行う。
次の話を読む:11月17日14時配信予定
*小見出しなどはWeb掲載のために加えたものです
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら