調理については、「聘珍樓」出身の料理長が各店の店長に技術を教え、それをそれぞれの店長が各店のメニューに落とし込んでいくというやり方だ。あえて非効率なやり方をすることで、それぞれのお店の特徴が生まれる。
餃子やシュウマイなどはセントラルキッチンで仕込んで各店に配送しているが、なんと工場では1個ずつ手作業で作っている。手作りなのだ。すべてにおいて機械を取り入れるわけではなく、味や、職人の負担など、さまざまな観点からベストを選択していく形だ。
まさに「ネオ町中華」的な店づくり。老舗の町中華の事業承継は「大阪王将」が手がけているが、「萬龍」は“文化”として町中華を残す手法である。

「東京ドームシティもそうですが、こういったエンタメ感のある場所で町中華は求められると思います。価格も1人2000円台までいくとなかなか日常的にはなりません。
一方で、町中華は手軽に友達や家族で何品か頼んでシェアもでき、かつSNS的なエンタメ性もあります。我々も『萬龍』のブランディングを通してチャーハンの魅力を再認識しました」(鳥生さん)
ヤケクソ感から生まれた「肉玉炒飯」は看板メニューに
そんな「萬龍」の看板メニュー「肉玉炒飯」は、コロナ禍でのヤケクソ感から生まれた商品である。

酒類を提供できなかった時期に、とにかくお客さんに元気になってもらえる食べ物をラインナップしようとして生まれた商品なのだ。大盛りのチャーハンの上にふわふわの卵焼き、そして大量の豚バラを乗せ、横にはシュウマイを2つ添えた。
「こだわりのシュウマイを横に置いてしまうというヤケクソ感は、コロナ禍でなければ思いつかなかったと思います。『元気にご飯を食べよう』『ガッツリ食べよう』というシンプルなメッセージです。一見雑な感じの見た目ですが、見ただけで脳に響くウマそう感にこだわっています。お酒を出せなかったので逆にターゲットが絞りやすかったのも大きかったです」(鳥生さん)

日常食を中心に提供している会社としては、お酒をしっかり売ることが一つの大きな課題になっている。今後はお酒×町中華メニューをさらに追求していきたいという。
「人手不足、人口減少、仕入れの高騰など外食自体は今危機的な状況です。その中でお客さんに選んでもらえる店だけが残ると思っています。お客さんのニーズを細かく感じながら、さらにブランドを伸ばしていきたいと思います」(鳥生さん)
町中華が消えていくなかで、それを持続可能な形で残そうという、イートアンドグループの試み。「資本系だから」「機械を使っているから」という先入観で判断する時代では、もはやなくなっているのだ。

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

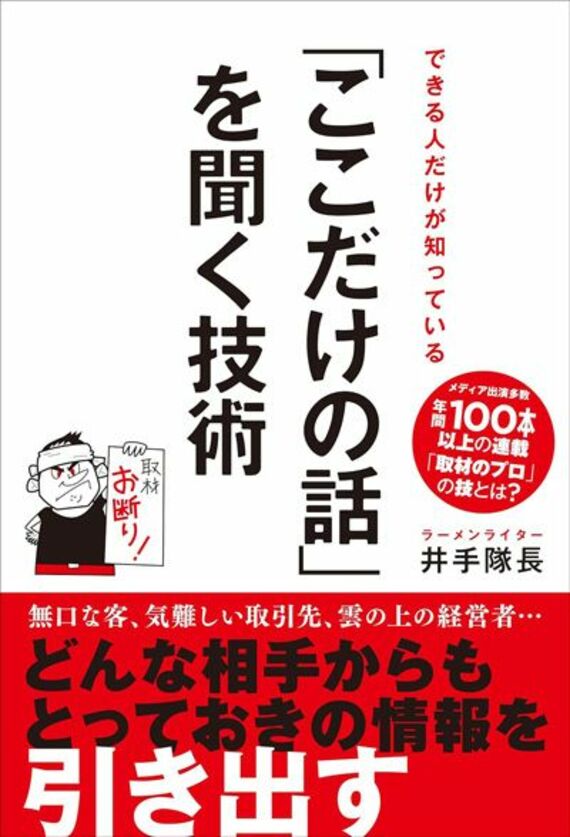






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら