
脳は情報を「数十秒」しか記憶しない
会議や商談で具体的な数字がパッと出る人、全然出ない人がいます。
必要なときに細かい情報がすぐ出る人は、その場で信頼を勝ち取ることができる可能性がグッと上がります。
逆に「後ほど調べて送ります」と情報伝達が後回しになると、千載一遇のチャンスを逃してしまうかもしれません。
大事な情報を覚えられる人と、覚えられない人で何が違うのでしょうか。記憶のメカニズムを解説していきます。
今回は、記憶がつくられる仕組みについて、わかりやすくお伝えします。
まず、記憶を保持するための2つの「貯蔵庫」について、お話しさせてください。
そもそも記憶についての研究は「認知心理学」という心理学の分野で、主に行われてきました。
認知心理学を一言で定義すると、人間を「高レベルの情報処理システム」と見なし、そこで行われる情報処理のプロセスを解き明かすことで心的活動を理解しようとする学問です。
認知心理学の世界では、記憶を保持期間の長さによって2種類に分類しています。
1つは30秒~数分程度しか覚えておくことができない「短期記憶」。
そしてもう一方が、より長期にわたり覚えておくことができる「長期記憶」。
つまり、脳に入ったあらゆる情報は、このいずれかに分類されることになります。

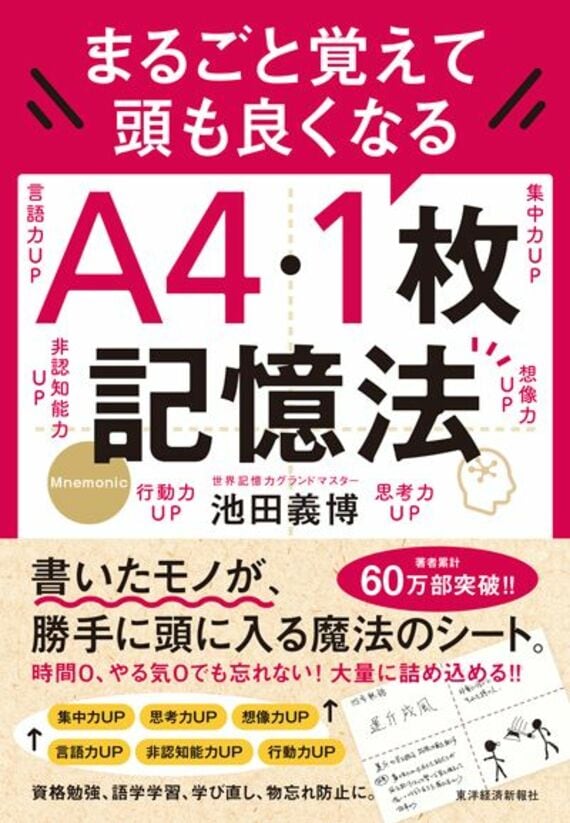






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら