
なぜ訴訟にまで発展するようなトラブルが起きるのだろうか。スルガ銀行が日本IBMを相手取って起こした訴訟など、システム開発をめぐる数多くの訴訟を担当してきた日比谷パーク法律事務所の上山浩弁護士に話を聞いた。
――システム開発をめぐって、発注者である企業と、開発者であるベンダーやコンサルティング会社との訴訟が相次いでいます。
確かに増加傾向にあるが、訴訟にまで発展するのはあくまで氷山の一角だ。訴訟になる前にユーザーとベンダーやコンサルとが話し合い、和解しているケースは多数ある。ユーザーが3桁億円の賠償を請求した案件で和解しているケースもある。ただベンダーやコンサルは、「うまくいかず、賠償金を支払った」と言われることを極端に嫌うため、和解に当たってはガチガチの秘密保持条項をつけている。だから表沙汰になっていないだけで、賠償金を払っている案件はかなりの数に上る。
――そうした中で外資系のベンダーやコンサルを相手取った訴訟が目立ちます。
国内のベンダーやコンサルは、追加費用さえもらえれば、なんだかんだいっても最後までやるところが多い。一方で外資勢は、追加費用を払ってもらったとしても赤字になるなら途中でもやめようという考え方に立ち、訴訟もいとわない。
なかでも日本IBMなどは判決を恐れていない。だから目立っているだけで、国内勢も数多くのトラブルを抱えている。
トラブルになるのは期限、費用、機能
――どういった理由でトラブルになるのでしょうか。
トラブルになるのは期限と費用、そして機能だ。簡単にいえば、当初ユーザーとベンダーやコンサルが合意・想定していた期限内に終わらないばかりか何度も延期が繰り返され、それに伴って想定の何倍もの費用がかかってしまう。にもかかわらず、約束していた機能が付加されておらず、「こんなに時間と費用をかけたのに、これまでのシステムと何も変わらないではないか」とユーザーが怒ってトラブルに発展してしまうのだ。





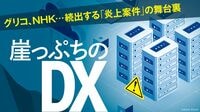





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら