「休めない日本人」いまだ生み出す抵抗勢力の正体 小室淑恵「現役時代の休み方が定年後を決める」

小室淑恵氏が「休む」ことの重要性を痛感した大失敗
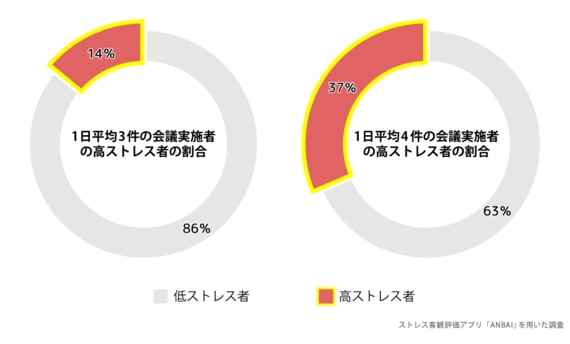
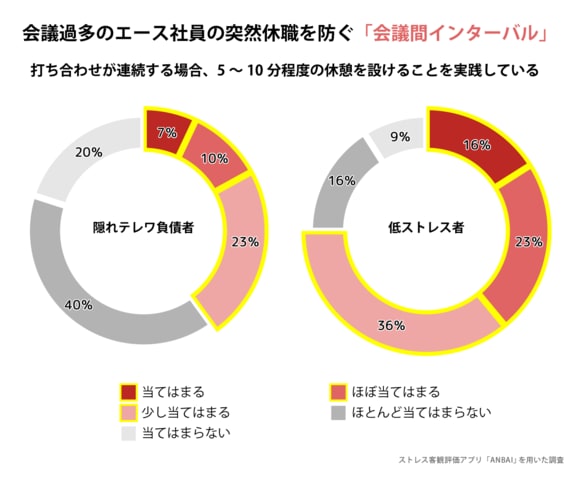
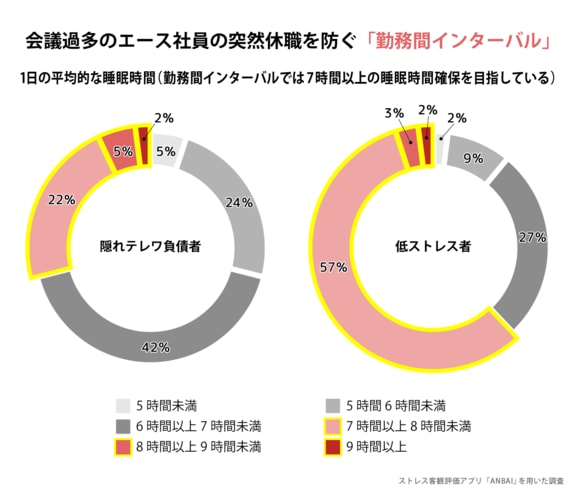
鈴木 裕介(以下、鈴木):私は臨床現場で患者さんにお休みすることを提言する立場にいます。しかしこれまでの経験から、休むことに対して、申し訳なさや恥ずかしさ、恐怖といった心理的ハードルがあると感じてきました。
疲労がたまりすぎて危険な水域に入っていても、休職などまとまった休みを取ることに対する抵抗が強い方はとても多いです。ある方は、休職することに「目標や指示もない部署にいきなり放り込まれるような怖さ」を感じるとおっしゃっていました。これまでの日常から切り離されて、先の見えないところに飛ばされる恐怖があるのだと考えています。
また、その方の性格や状態にもよりますが、罪悪感を持たずに“ただ休む”ことができるようになるまでだいたい1カ月くらいはかかるんですね。
その後、やっと自分の体にとって休むことが大事だと実感できるんです。その経過を見ていると、休んでみないとわからないことがあるんだなと、常々患者さんから学んでいます。
小室 淑恵(以下、小室):私自身は元々は、仕事をどこで終わりにするか線が引けないタイプでした。前職では持ち帰りの仕事は当たり前。ですが、長男を出産後、同じスタイルは継続できないとすぐにわかりました。
































