
「私が職場やCPで得られた『つながり』による安心感と生きる力を、2つのサロンを通して、皆さんに少しでも感じてもらえたらなと思います」
そう話す松本さんは、がんになる前から前向きな人間だったが、さすがに「患者サロンを始めます!」というタイプではなかったと明かす。
「ですがステージ4と宣告され、『本当に死ぬかもしれない』と追いつめられ、娘たちへ遺書まで書いてみて気づいたんです。このままやりたいこともせずに後悔したくない、もっと自分らしく生きたい!って」
いのちの反発力が背中を押していた。
「仕事が趣味」の母親から娘たちが学んだこと

実は、松本さんは治療入院する前日まで仕事をしていた。それほど自他ともに認める仕事好き。27歳の長女と13歳の次女からも「お母さんの趣味は仕事でしょう!」と、発症前から言われていた。
反面、自分の背中を見て、娘たちが育っている手応えもある。
「長女が助産師を志したのは、私が15歳下の次女を産み育てる様子を、ちょうど思春期に目の当たりにしたからなんです。自分もそうして育てられてきたと気づき、多感な年頃になって減り気味だった母娘の会話も、次女の育児をきっかけに増え始めましたし」
助産師の長女は、家庭では弱音を一度も口にせず、大学医学部附属病院で頑張って働いている。

中学2年生の次女は、小学6年生の夏の自由研究で、肺がんについて調べて、「お母さん、ヤバかったんじゃん!」と改めて驚いていた。
小学校の卒業文集には、「患者さんや家族を支えて笑顔を広げる看護師か、お姉ちゃんのような助産師になりたい」と書き、担任教師から「患者さんだけでなく、家族のことまで考えている点が素晴らしい」と褒められた。
「私に起きた出産やがんという出来事を通して、2人の娘たちがそれぞれに何かを学びとってくれたのは、よかったなぁと思います。そうやって子供たちが成長してくれていることが、私の宝物ですね」(松本さん)
がん告知から約4年。内服薬の副作用で味覚障害があり、果物やヨーグルトを苦く感じたり、皮膚に湿しんが出たりはする。だが、仕事をするうえでの障害はとくにない。
肺腺がんになってよかったとは思わない。
だが、好きな仕事では新たな責任を与えられ、娘たちの成長や、同病者の方々とつながることで広がった関係までふくめれば、すべてが悪かったわけではないと松本さんは思っている。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


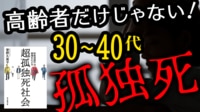






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら