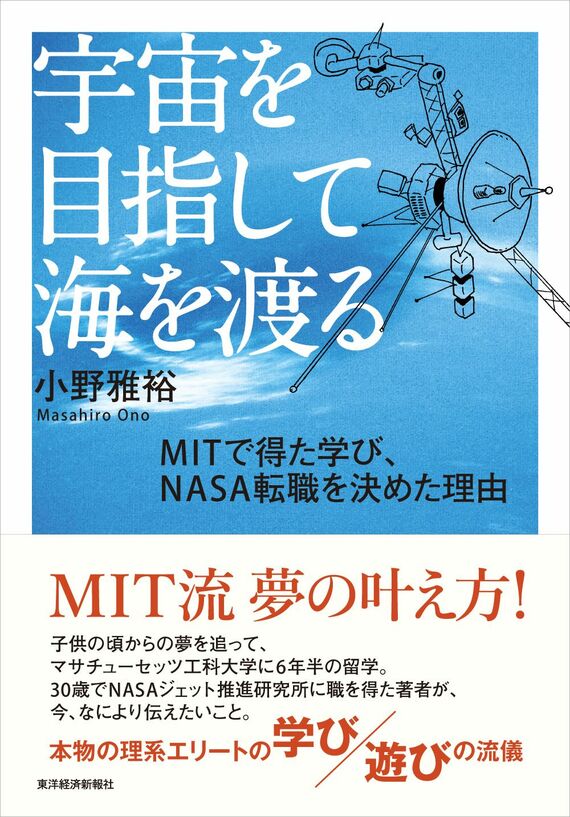
前回の記事("技術志向"がNASAで通用しない理由)では、勤めて一年になるNASAジェット推進研究所(JPL)におけるプロジェクト・ベースの職場の仕組みを紹介し、その中で「プチ失業」をするという失敗体験をしたことをお話した。
そして、その体験から、目的志向の技術の売り込み方を学んだことを書いた。今回は、そこから学んだもうひとつのこと、すなわち組織内における「自分の売り込み方」についてお話しようと思う。
新入りという立場にある者は、何事も不慣れであるが故に、何かと過剰反応してしまうものである。僕の「プチ失業」も、NASAジェット推進研究所に転職してから1年経ってみて、どうやらそんなに大げさに言うほどのものではないことがわかってきた。
というのも、プロジェクトやタスクが切られることは日常茶飯のことなのだ。花でも生けるかのように、気軽にチョッキンチョッキンと切る。
いちいち研究所全体の合意を取らなくても、その研究費の責任を持つマネジャーの裁量で切ることができる。切る側は切られる側に相談する必要はないし、事情を気にする必要もない。
何かを切ることは、必ずしもそれが不要だったり、またそれを担当する人が無能であることを意味しない。ただ、優先順位が比較的低いものの予算を、優先順位が高いものに回すためのオペレーションでしかない。つまりは、気軽に切れるということが、この組織の柔軟性を確保するための仕組みなのだ。
(余談だが、そうはいってもやはり“too big to fail”というのはあるようだ。JPLではなく、NASAのほかのセンターが担当している計画だが、ハッブル宇宙望遠鏡の後継であるジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、当初予算の16億ドル(約1600億円)を4倍も超過し、議会が予算をカットしようとしたものの、結局は継続ということになった。)

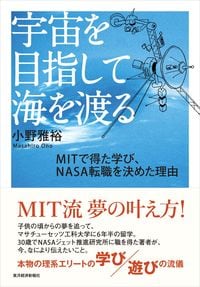
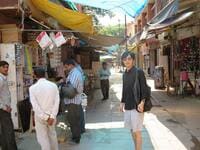





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら