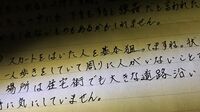《財務・会計講座》「村上ファンド」の功罪~企業価値を回復するための株主のあり方~

バブルが崩壊するまで、日本企業は相互に株式を持ち合うことで企業経営の安定を保ってきた。その中核を担っていたのは大手銀行や生命・損害保険会社で、彼らは取引上のメリットを狙って事業会社の株式を大量に保有していた。企業側から見れば、少なくともある程度の経営成績を出している限りは、彼らはモノを言わないやさしい安定株主であった。
しかしながら、そうした株式の持合構造は、バブルの崩壊とともに終焉を迎えた。ここに登場してきたのが外国の機関投資家やファンドである。
海外の年金基金やファンド等を中心とした海外投資家にとっては、投資先の企業に意見を述べるのは当たり前であり、株主を軽視した経営を行っていると感じられる企業には、株主総会で会社提出議案に反対票を投じたり、企業経営者に直接意見を具申したりしている。このような投資家はアクティビスト(活動的投資家)と呼ばれており、それまで安定株主との関係に慣れていた日本企業には、彼らの台頭は衝撃的であった。
■株主として過激な意見を述べながら「会社は誰のものか」を世に問うた
さて、本題の村上氏と村上ファンドであるが、彼らの本質は何だったのであろうか--。村上氏に対する世の中の評価は大きく分かれる。株主軽視の企業経営者にモノを言うアクティビストであると評価する声がある一方で、標的にした企業やその関連会社に高値で買い取らせることを目的に株式の買い集めをおこなうグリーンメーラー(敵対的買収者)だという批判もある。
そんな村上氏の“戦い”は、2000年の昭栄株式会社の株式取得から始まった。同社はもともと生糸製造者として昭和6年に設立された長い歴史を持つ企業で、JR駅前などの一等地を中心に多くの土地を所有し、他の上場企業株式も保有する東証二部上場企業(当時)であった。しかし、保有する膨大な資産の有効活用が進んでおらず、結果として株価も低位で放置されていた。
その状況に目をつけた村上氏は、同社に対して遊休不動産や株式の有効活用を求め、TOB(Take Over Bid、株式の公開買い付け)を仕掛けた。これが日本初の敵対的TOBであった。ところが同社には当時の富士銀行やキヤノンを中心とした芙蓉(当時の富士銀行)グループ企業が大株主としてバックについており、また同社の経営陣も不採算事業からの撤退を含む業績改善方針を発表したことから、村上ファンドによるTOBは結局失敗に終わった。
その後の昭栄を見てみると、直近期(2006年12月期)の業績は、売上高が242億円(2000年12月期は109億円)、税引後当期純利益が55億円(同6億円)、株主資本が635億円(同82億円)、株式の時価総額が1232億円(同212億円)と、保有資産の徹底活用によって敵対TOBにあった2000年頃とは見違うばかりの高収益会社に生まれ変わった。この大変身のきっかけを作ったのが村上ファンドと言っていいだろう。
村上ファンドの次の標的は株式会社東京スタイルであった。東京スタイルは2001年当時、連結売上高が625億円、営業利益48億円、当期純利益47億円、そして株主資本(簿価)が1576億円のアパレルメーカーであり、1360億円に上る現預金・有価証券・投資有価証券を保有していた(2002年2月期実績)。
同社はその頃、豊富な余裕資金を活用するためにファッションビルを購入する計画を発表していた。これに対し村上ファンドは同社株を買い増し、2002年5月の同社株主総会において企業価値向上の視点で大胆な提案をした。その内容とは、(1)ファッションビルへの500億円の投資を中止すること、(2)現預金・有価証券を原資として自社株買いを行うこと--であった。
これに対抗して同社の経営陣は増配と小規模ながらも自己株買いを提案し、大株主の支持を取り付けようとした。対する村上ファンドは、外国人株主と個人株主を味方に引き入れようと、壮絶な委任状争奪戦を繰り広げた。結果は村上ファンドの惨敗であったが、今考えると、村上ファンドの主張が当時の東京スタイルの株主(ひいては日本の株主全般)にとって過激すぎて理解ができなかったために敗北を喫したのだろう。
この事件を契機に日本でも、株主の利益のあり方、さらには「会社とは誰のものか」といった株式会社の本質を問う流れが確実に生まれたといってよい。
なお、その後の東京スタイルは、2006年2月期の実績を見ると連結売上高554億円に対し、営業利益30億円、当期純利益39億円と業績は停滞している。一方、株主資本(簿価)が1678億円、現預金・有価証券・投資有価証の合計は1592億円と当時とあまり変わっていない。村上ファンドの敵対的TOBを契機として大変身を遂げた昭栄とは対照的である。
■株主を軽視する企業に圧力をかけ企業価値の毀損を回復
村上ファンドはその後も、アクティビスト株主として多数の企業の株を買い集め、経営者にプレッシャーをかけていった。以前このコラムでも説明したが、日本には最近まで、株主資本比率の高さが安定性の象徴とばかりに、活用するあてもなく過剰な現預金を貯め込む企業が多かった。こういう企業には、純資産倍率(PBR、株価が1株あたりの簿価の株主資本の何倍で取引されているかを示す指標)が1倍以下であり、豊富な現預金を持ちながらも解散価値が現預金の額に満たないといった状態にあるところが相当数あった。
この点に目をつけたのが村上ファンドであり、その後のスティール・パートナーズといった投資ファンドである。
企業価値そして株主価値の向上に目を向けない企業の株を買い集め、経営者にプレッシャーを掛けることで、余剰キャッシュを増配や自己株式の買い取りの形で会社の外部に放出し、それまでの企業価値の毀損を修復するというのが彼らの手法であった。
この過程で村上ファンドは大きな株式売却益を手にしていった。この素晴らしい運用実績を見て、海外の大学財団や国内の機関投資家や企業は高利回りを期待して村上ファンドに多額の資金を預けるようになり、2006年初めにはファンドの規模は4000億円を上回るまでに成長した。なお、1999年の村上ファンドの設立時に、当時富士通総研理事長であった現日本銀行総裁の福井俊彦氏が1000万円出資していたことが判明し、世の中を騒がせたことは記憶に新しい。