親を亡くした人が、生前の親の顔を思い浮かべたり、小さな遺影に話しかけていたりすることがある。柴田会長の死生観はその延長線上にある。
「あれはお母さんじゃない。もう私のここにいる」

「生まれて初めて臨終に立ち会い、私の場合、それが妻だったわけですが、一番近くで体感した今、死はもう怖くないです。5カ月ほどが過ぎた今でも、ずっとそばにいるような気がしますから」
加藤は、美咲の看取りについてきっぱりと語った。
普段から妻とはスキンシップを取っていて、看取り士の大橋から事前に抱きしめて看取ることも聞いていたので、違和感はなかったという。
「手脚はすぐに冷たくなっても、背中は亡くなってから3時間半ほどは温かったですよ。残り1カ月は苦しんだ闘病生活でしたけど、最期はとても穏やかでしたし、大橋さんたちのおかげで、満点の看取りができました」
美咲の告別式から約2週間後。大橋は加藤から、冒頭の10月5日の病室で、子供たちが冷静だった理由を初めて明かされた。
実は同3日の夜、加藤は、美咲に子供たちとのお別れをさせていた。野球部の寮で暮らす中学1年の次男を除く、4人の子供たちを、美咲は一人ずつベッドに呼んで抱きしめて言葉を交わしたという。
「お母さんは魔法使いになって、いつもみんなのそばにいる。苦しいときは苦しいと言いなさい。お母さんがすぐに駆けつけるけんね」
子供らはみんな泣いていたが、美咲は満面の笑みで一人ひとりに力強く伝えていく。最後に一人娘で、小学1年の美春を呼んで尋ねた。
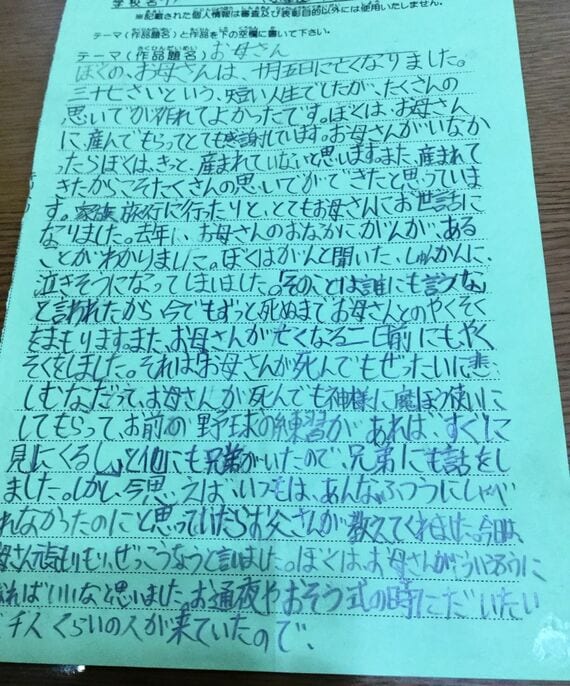
「お母さんの宝物は何?」
「美春!」
「お母さんが、一番大好きなのは誰?」
「美春!」
「ちゃ〜んとわかっとるけん、大丈夫ね」
答えながら泣く娘を、母はぎゅっと抱きしめた。娘は添い寝をせがんだ。
「あの夜の妻の、『魔法使いになって、いつもみんなのそばにいる』という言葉を、みんな、信じているんです。だから妻が旅立った病室に来たとき、子供たちは強かった。俺、子供たちを尊敬しますよ」
加藤はハンカチで目頭を何度も押さえながら、そう絞り出した。
5日は、加藤の「遠方から駆けつける次男の到着を待ってほしい」という希望を受け入れ、医師は死亡確認を次男の到着後に行うことに同意。病院では珍しい約3時間半の看取りが実現した。
告別式を終えて火葬場から帰る8日の午後のことだ。美春は3日の病室だけでなく、自宅から出棺する当日も、母親の体に一度も触れなかった。少し年上のいとこからその理由を聞かれた美春は、小さな胸に手を当てて話したという。
「あれはお母さんじゃない。もう私のここにいる」
(=敬称略=)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


































無料会員登録はこちら
ログインはこちら