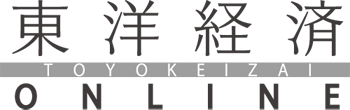伝説のプログラマーが守り切る誠実な生き方 永遠のパソコン少年が突破した壁の先
――「必ず元を取る」と(笑)。
中島氏:なぜか直感で、「絶対にそうなるはず」という、根拠のない自信があったんですね(笑)。ところがプログラミングに触れた最初の1ヶ月間、これがさっぱりわからなくて。「どうして、そのようにプログラムを入力すれば、こう動くのか」。教科書もありませんでしたから、とにかく仕様書のサンプルコードや、雑誌に載ってあるプログラムコードと、にらめっこの日々が続きました。
来る日も来る日も仕組みがわからない。けれど不思議と諦めることはありませんでしたね。結局のところ、プログラミングは概念・思考プロセスの理解の問題なのですが、それがわかったのは本当に突然でした。壁を叩き続けていたら急に崩れたような感覚で「なんだ、そういうことか」と。それからですね、プログラミングが楽しくなったのは。その時の道がパッと拓けたような感覚は今でも鮮明に覚えています。
――「壁」を突破した先にあったものは。
中島氏:とことん没頭できる幸せな時間でした。もうそれからは寝ても覚めても、プログラミング一色ですよ(笑)。プログラムでできるものは何でもやっていましたね。当時、コンピュータ雑誌の『月刊アスキー(ASCII)』と『I/O(アイオー)』を愛読していましたが、自作のアセンブラやディスアセンブラ(いずれもプログラミングのためのツール)を、編集部の住所を調べて、アポなしで「できました!」って持ち込んだこともあります。別に頼まれた訳ではなかったのですが、それで雑誌に掲載されればいいなと。最初はそんなところからのプログラミング人生のスタートでした。
こうした自由な時間が確保できていたのも、受験のための勉強をしなくてよかったからだと思います。ぼくは決められた「勉強」をするのが苦手で、それよりも自分の好きなことに没頭したいと考え、高校は早稲田の高等学院に進んだんです。これで後々、大学受験のための勉強はしなくて済むと。東大志向だった親からしてみれば、「アレ?」と肩すかしを喰らったでしょうが、思えば、この時からすでに人の言うことを聞いていなかったのかもしれません。おかげで、そのまま大学、大学院と進みながら、自分の好きなプログラミングに没頭し続けることができました。
自分の感情に誠実であることの大切さ
中島氏:この頃には、科学者になりたいという夢も変わり、すっかりコンピュータに魅せられていました。当時、週刊アスキーの編集長だった吉崎さんもヘンテコな高校生プログラマーを可愛がってくれて、高校生ながらアルバイト記者として働いていました。
大学はそのまま早稲田の電子通信学科に進んだのですが、コンピュータのことはほとんどアスキーでの仕事で学んでいました。学部生の頃、「CANDY」という世界初のCADソフトを作ったのですが、これも直線を引くプログラミングで遊んでいたことと、アスキーの古川さんからのマウスをPCに繋げられるソフトウェアの依頼を受けていたこと、それに自分の卒論でのアイディアが融合してひらめいたものでした。
それまでもさまざまなソフトウェアを開発していたのですが、権利も曖昧で誰でも使用できるオープンソース的な使われ方だったんです。「CANDY」の時はさすがにロイヤリティ交渉をして、初年度で数千万円、翌年には1億円近いロイヤリティを得ることができました。