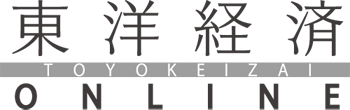高級ミニカーに魅せられた男の並外れた情熱 知らなくてもいいが知ろうとしないのは罪だ
――失敗を糧にしながら学んでいく。
小林氏:そうやって仕事の厳しさと喜びを学んでいく中で、次の転機は不意に訪れました。知り合いの車の買い替えのタイミングで、安く譲ってもらったホンダのプレリュードが初めての愛車だったのですが、毎週磨いているうちに、またムクムクと車への想いが再燃してきた頃で、車の雑誌を何冊か定期的に買っては読み漁っていたんです。単純に車の情報を読むのも好きだったのですが、記事構成や企画内容、誌面上でおこなわれるキャンペーン企画の展開の仕方など、そちらの方に興味を持っていて「新卒の時は叶わなかったけど、やっぱりこういう仕事をしてみたいな」と、漠然と思い描いていました。
その頃、すでに結婚をしていたのですが、ある日曜日の朝に、妻から「そういえば先週の新聞に、車雑誌の求人広告が出てたよ」と言われたんです。それを聞いて急いで探し出すと、募集は新卒、中途とも若干名とありました。ダメ元で受けてみようと思ったのですが、課題作文だった「自分がやってきたこと、やりたいこと」を自宅で書いてみて、そこで妻から大量の赤字で訂正が入ると、だんだんと真剣になっていきました(笑)。
妻の鬼の赤字のおかげで、面接まで漕ぎ着けたのですが、その帰りに職場となる編集部を見せていただく機会がありました。その瞬間、「ここで働きたい!」と、理由はよくわかりませんでしたが、ものすごい衝動を感じたんです。最終面接の結果は電話でいただけるようになっていたのですが、待てど暮らせどかかってこず、いても立ってもいられないのでこちらから電話をかけてみると「ちょうど今、採用連絡をするところでした」と。そうして、私の編集者としてのキャリア、車を軸にして生きていく人生は、ひょんなことからスタートしました。
雑誌づくりは“お祭り”
――躊躇なき行動が、結果を運んできてくれました。
小林氏:新卒2名、中途採用は私1名でした。現場はまさに昭和の編集部。「最初はスーツで仕事」と聞いていましたが、最初の3日間でネクタイなんてしていられない状況だということが、すぐに分かりました。隔週刊の雑誌だったので、月に2回やってくる締め切り、そのゴールに向かって、編集部一丸となって突進していく姿。大きな出版社ではなかったので、企画出し・取材はもちろん、デザインラフ作り、執筆、校正など、あらゆることをみんなでやっていくんです。それは、さながら夜通し続くお祭りのようで、今の基準に照らし合わせれば「とんでもない」という評価になると思います。けれど、自分はそうやって一所懸命汗水たらして働くことが楽しくて仕方がなかったんです。
もちろんいいことばかりでなく、編集長から「こんな原稿つまらん」と、何度も突き返されて悔しい想いもしましたし、発行部数30万部の先にいる読者の期待、プレッシャーも感じていました(もちろん数字だけではありませんが)。そんな状況でも、まわりは皆、目が生き生きとしていたんです。おそらく当時の自分も同じだったと思います。体力的にもキツイはずなのに、仕事終わりに編集部の仲間と恵比寿にあったミニカーショップに繰り出すのも楽しかったですし、何より嬉しかったのは取材のために、あらゆる車種の車を運転できたことでした。この時、「好きを仕事にする楽しさ」を実感しましたね。