――映画の世界にはまり込んだ理由は?
大学時代は写真サークルに所属していて、建築学科よりもサークルのほうに熱心な学生でした。自分は社会人になってもずっと写真を撮り続けていたのですが、ある日、この写真が動き出したら面白いなと思うようになりました。それから、動き出した写真に音楽が入ると面白いなとか、頭の中でどんどん想像が膨らんでいった。それが映画を撮ろうと思ったきっかけです。友人たちと8ミリフィルムで、映画を撮り始めましたが、だんだん欲が出てきて、短編映画を撮るようになりました。
そうこうしているうちに、趣味ではなく、きちんとした映画を撮っておかないと、きっと後悔するぞと思うようになった。そして会社を辞め、本格的な短編を1本撮った。そして、それから映画の世界に入ることを決めたのです。
巨匠の「本腰を入れてやれ」の一言が大きかった
――監督のプロフィールには、韓国映画界の巨匠、ポン・ジュノ監督の2003年作『殺人の追憶』のスタッフをやりながら映画を学んだと書いてありました。それはその頃の話なのでしょうか?

1本短編を撮った段階で、映画の世界に戻るか、建築の世界に戻るか。あらためて悩んみました。ちょうどそのとき、ポン・ジュノ監督の演出部の方から、6カ月ほど一緒に仕事をやってみないかと誘われた。そこで6カ月やって駄目だったら建築に戻ればいい、という気持ちで参加したのですが、結局、その仕事は2年もかかってしまいました(笑)。2年も経過し、私が建築の世界に戻るには、あまりにも遠い場所になってしまった。だからそのまま映画の道に進むことに決めたわけです。
ただ当時、あまりにもおカネがなかったので、設計事務所の先輩が見かねて、自分のところでバイトをしないかと誘ってくれました。でもそれを聞いたポン・ジュノ監督が「映画をやるからには本腰を入れてやれ! しっかりとしたシナリオの準備をするほうがバイトよりも大事だ!」としかってくれたのです。結局、バイトもせずにシナリオを書くことに専念することになりました。そこが僕のターニングポイントでしたね。
――ポン・ジュノ監督の激励がなければ、この『建築学概論』は生まれなかったということですね。
彼は精神的にもずいぶん支えてくれました。あれは2003年のことでした。ただ、このシナリオ自体は10年近く書き続けてきたのですが、なかなか制作にこぎ着けられませんでした。ポン・ジュノ監督にしかられてから6、7年後、ポン・ジュノ監督もしだいに責任を感じ始めるようになりました。このまま僕がものにならなかったら、これは自分のせいだと。ずいぶん気をもまれたようです(笑)。
――10年もの間、どのようにしてモチベーションを持ち続け、自分を鼓舞していったのでしょうか?
僕のやり方はとても非経済的なので、あまり人に勧められるようなものではありませんが(笑)。僕も最近、講演を頼まれるようになり、そこで若い人たちにアドバイスを送るような機会が増えてきました。彼らを見ていると、15年前の自分の姿と重なって見えるのです。彼らは、やりたいことがあるのに、それをやったら人生を踏み外してしまうんじゃないか、人生に失敗してしまうんじゃないかというおそれを持っている。もちろん僕自身だって、そういったおそれがなかったかと言われればウソになる。決して何かが保障されていたわけではないですからね。

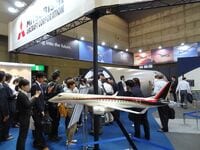






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら