「わざわざ飛びながら眠る」鳥がいる理由とは?動物の≪睡眠にまつわる疑問≫を東大准教授が解説!人間の”ぐっすり眠る”も実は習性ではない?
カツオやマグロのような回遊魚も泳ぎながら眠っている。水族館の回遊水槽で夜間に見られるそうだが、泳ぎながらフラフラと横向きや仰向けになってしまう。ただし、ほんの数秒でまた正しい姿勢に戻るので、彼らも数秒ずつの細切れの睡眠を取っているようだ。
一方、ショウジョウバエは暗黒条件だと10時間以上も活動を休止する。オランウータンやチンパンジーなど大型類人猿も、人間並みに長い間眠る。魚類でも、ベラやキスは日が暮れるとお行儀よくさっさと寝てしまう。ベラの仲間には、まるで布団に入るように砂に潜って横になる種までいる。
人間が「朝までぐっすり眠る」は習慣か? 習性か?
ただ、チンパンジーは夜の間に何度か目を覚ましているとのことだ。
さらに言えば、人間の睡眠だって「夜から朝までずっと寝ている」というスタイルになったのは、朝から夕方まで定時で工場労働するという産業構造が定着したことによるのではないか、という意見もある〈座馬耕一郎『チンパンジーは365日ベッドを作る 眠りの人類進化論』ポプラ新書〉。
古い記録を調べると、夜中に一度起きてちょっとお喋りして、お茶を飲んでまた寝るのが習慣になっていた例などもあるようだ。昼寝の習慣もよくある。
ヒトの睡眠時間が長いのは確かだが、「夜になると朝までぐっすり眠る」という現代人の常識が、ヒトという生物種の習性そのものとは限らないようだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

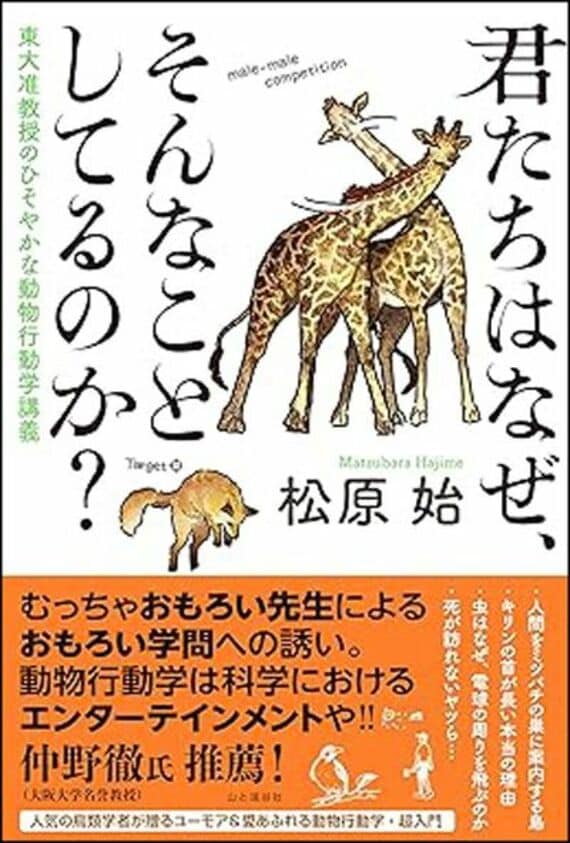






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら