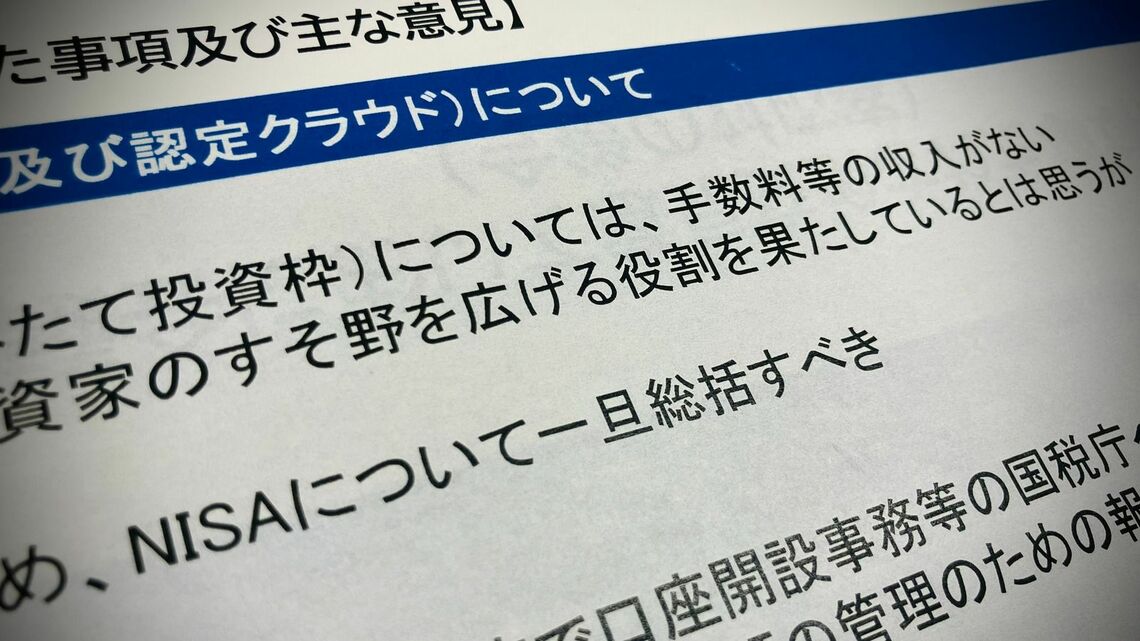
新NISAを拡充する議論が進んでいる。金融庁が8月に公表した2026年度の税制改正要望では、NISAの対象となる商品の拡充や年齢の引き下げ、非課税限度額の年内の復活などが盛り込まれた。
これらはNISAの普及に資する改定案だが、当の証券業界の心境は複雑だ。とりわけ地方に拠点を構える中小の証券会社はさめた見方をする。ただでさえ経営環境が厳しさを増す中、NISAが経営体力を一層削りかねないからだ。
業界団体の会合では、「反NISA」を公然と訴える動きさえある。
「NISAのあり方を総括すべき」
「投資家の裾野を広げる役割を果たしているとは思うが、証券会社の費用負担が重い」「NISAについて、いったん総括すべきだ」
2月、東京都中央区にある太陽生命日本橋ビルの一室。日本証券業協会(日証協)が主宰した地場証券との意見交換会は、異様な雰囲気に包まれていた。関係者によれば、出席した地場証券の首脳がNISAへの不満を次々と口にし、事務局が議論の収拾に追われたという。
地方銀行が全国に所在するのと同様に、特定の地域でのみ営業する地場証券も全国にある。折からの人口減少で先行きが厳しい中、さらなる逆風となったのがNISAだ。「一種の『国策』だから協力しているが、証券会社にとってのメリットはほとんどない」。西日本の地場証券幹部は吐き捨てる。
根底にあるのは収益性の低さだ。つみたて投資枠の場合、対象となる公募投資信託の販売手数料はゼロ。信託報酬も0.3%以下が過半だ。人気商品である「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」に至っては0.05%で、このうち販売会社の取り分は0.0175%。1億円分を売っても、手数料は1万7500円しか入らない。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら