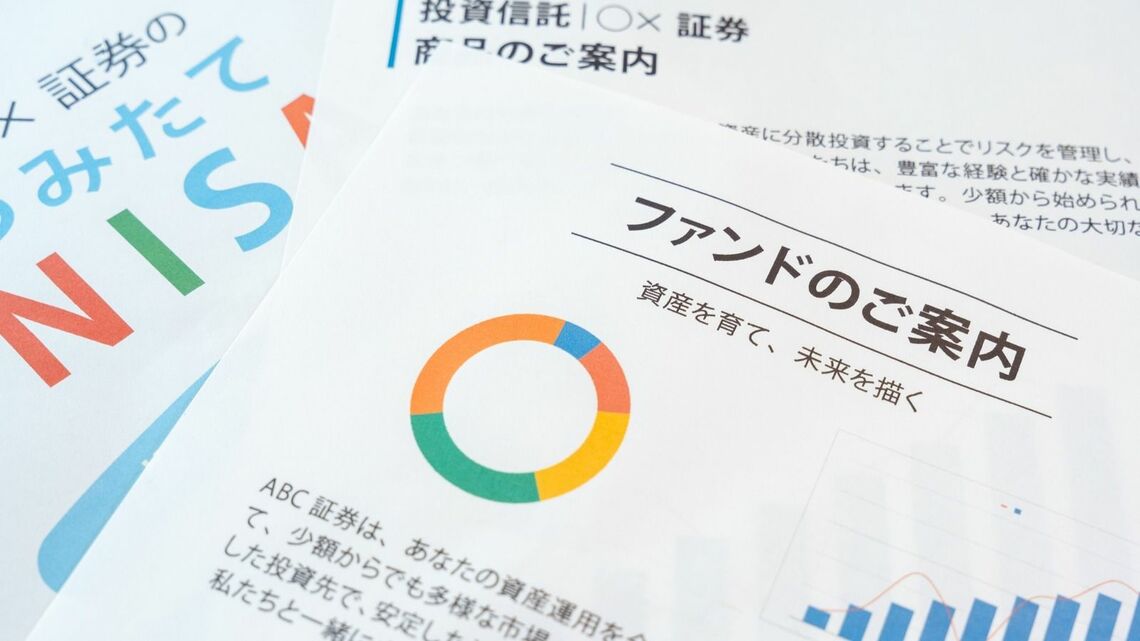
地方銀行や信用金庫などの地域金融機関で「投信販売離れ」が進んでいる。市況情報を提供するQUICKによると、地銀では2025年上半期(1~6月)の投資信託の販売実績が1兆6606億円となり、前年同期比20.4%減少した。
「4月以降のトランプ関税リスクで投資に二の足を踏む個人投資家が多くいたことが影響した」。ある地銀の担当者は販売実績の落ち込みをこう分析する。
ただし、投資信託協会の統計によると、同じ期間における市場全体の公募株式投信(ETF除く)の設定額(資金流入額)は9.2%の減少にとどまっており、地銀の販売実績ほど落ち込んでいるわけではない。金利が復活したことで預貸ビジネスを強化する動きが強まる一方、マイナス金利時代に収益を下支えした投信販売から距離を置く地銀や信金が出始めている。
低下する「売る力」
地銀の投信販売に詳しい佐山リサーチオフィス代表の佐山雅致氏は、「預金の重要性が増す中、地銀は預貸ビジネスにリソースを割くようになっており、投信を売る力が落ちている」と話す。今後についても「投信販売額は減少に向かう可能性が高い」と見通す。
投信販売の収益性低下も、販売力を弱める一因だ。売れ筋のインデックス型投信はノーロード(販売手数料無料)が大半になっており、販売した投信残高の信託報酬から得られる代行手数料率も低下傾向にある。
その一方で、投信販売は適合性原則の確認やリスク説明などに多くの時間を取られてしまう。貸し出しや国内債券運用の金利妙味が高まる中、その費用対収益効果は相対的に大きく見劣りする。


































無料会員登録はこちら
ログインはこちら