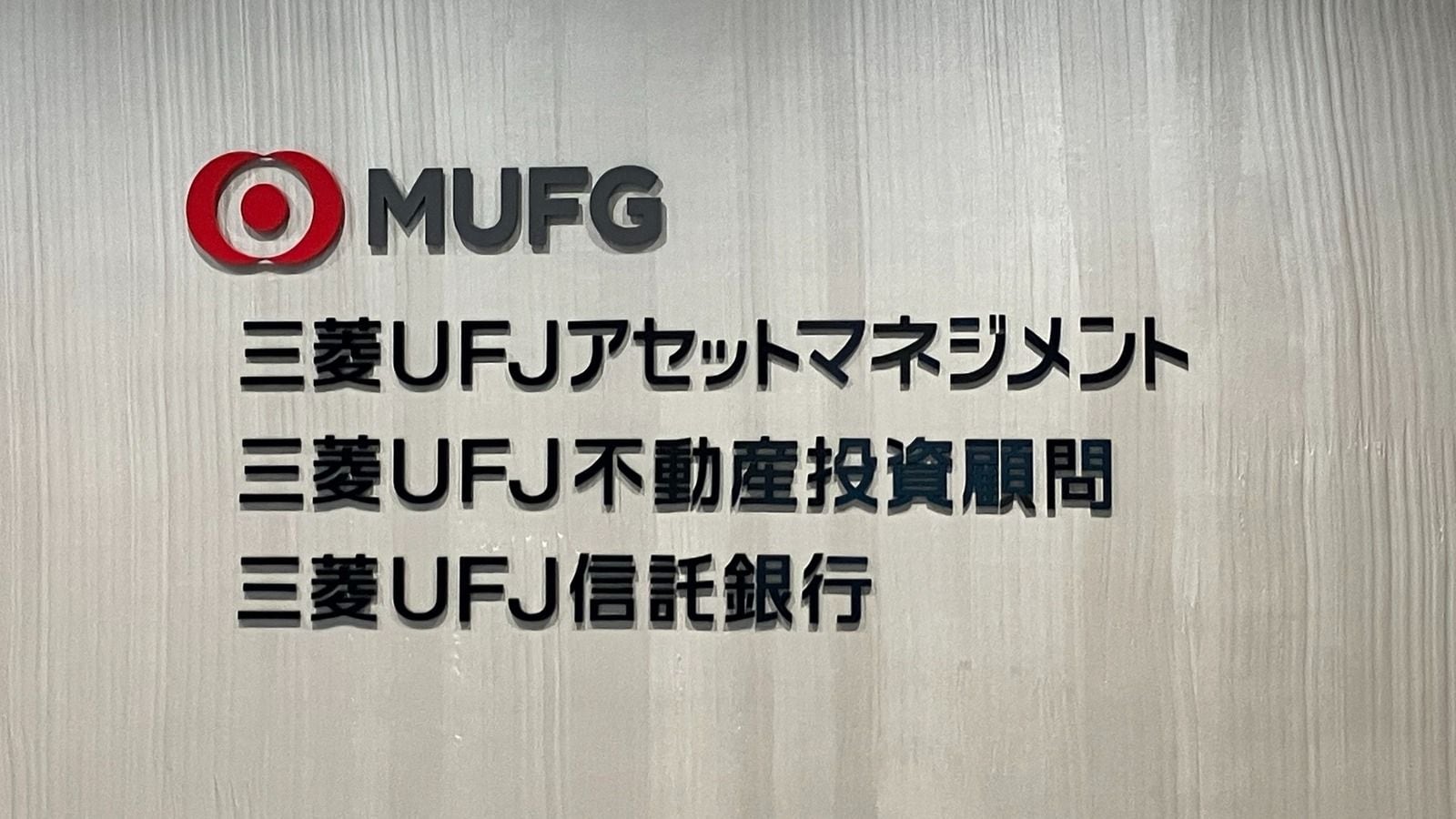
金融庁が指摘した"運用業界の闇"改善は進んだか
創設2年、東証「アクティブETF」に鳴く閑古鳥
「投信半減」に突き進む野村AMの反省とその先
地銀で進む「投信離れ」、運用業界は淘汰の渦へ
経営圧迫!地場証券で噴出する「反NISA」のマグマ など
新NISAや円安効果によって順調に資産残高を拡大してきた運用業界に異変が起きている。
投資信託協会の統計によると、7月の国内公募追加型株式投信(ETF除く)の純資金流入額は2502億円で、26カ月連続の「流入超過」となった。だが、純資金流入額が2.1兆円でピークとなった今年1月以降、流入額は減り続けており、7月はついに新NISA開始前の2023年12月(3053億円)を下回った。
「4月以降のトランプ関税の不透明感や、利益確定の動きが強まったことによるもの。個人の投資マインドは落ちていない」。大手資産運用会社のトップは、資金流入の鈍化はいずれ回復するとの見通しを持つが、もう1つの異変には神経をとがらせる。
株価指数などに連動するインデックス型のパッシブファンドに資金が集まる一方、市場平均以上の運用成績を目指すアクティブファンドで解約が目立つことだ。
パッシブ一辺倒に危機感
実際、7月は新NISAが始まって以来初めて、アクティブファンドが「流出超過」に転じた。資金流入の動きを見ても、近年はパッシブ一辺倒(下図)。投信評価会社の三菱アセット・ブレインズによると、今年1~7月の純資金流入額(8.41兆円)のうちパッシブファンドが約76%の6.37兆円に上り、アクティブファンドを大きく上回る。
アクティブ比率の低下は運用会社にとって収益面で打撃だ。パッシブファンドへの資金流入によって投信の純資産残高を維持できても、アクティブファンドの割合が下がれば大幅な減収になりかねない。



































無料会員登録はこちら
ログインはこちら