3766万円の一括返済が退職条件、想定しえない緊急事態が生じても一切の離脱や退職を許さない。自治医大訴訟で見えた医師「お礼奉公」の深い闇

女子差別が組織的に行われてきた医学部入試、大学院生の医師に無給で診療行為をさせていた無給医問題。働き方改革においても「過労死ライン」の約2倍の過重労働を医師のみに認めるなど、日本の医学教育、医師労働では人権上の問題が山積している。
自治医大独自の「修学金制度」
そんな中、新たに浮上したのが「修学金制度」の問題だ。今年3月、自治医科大学の元学生のA医師が、同大学の修学金制度が違憲・違法だとして、大学と愛知県を相手取り提訴した。自治医大独自のこの制度は、学費などを貸し付け、出身自治体に指定された僻地の病院などに一定期間勤務した場合、貸付金の返済を免除するというもの。同大学の入学者は全員必ず、貸与を受けることになっている。
A医師は大学から2660万円を貸与され、2022年の卒業後は出身の愛知県内の病院で研修医として勤務していた。ところが就労できない重い自閉症を抱える弟の病状悪化、父親の失職、妻の妊娠という予期せぬ事態が重なり、従来の勤務継続が難しくなった。
県からは「退職するならば損害金も含め3766万円の一括返済が条件。家庭の事情があっても減額、分割はいっさいできない」と告げられた。実際、24年の退職後、大学から返還請求を受けている。
裁判の主な争点は以下の3点だ。①病院を一方的に指定し、そこでの勤務を強要することは「居住の自由」(憲法22条)を奪う。②本制度はA医師を10年半も拘束するものであるため、有期の労働契約は医師の場合5年を超えてはならないとする労働基準法14条に違反する。③「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損額賠償額を予定する契約をしてはならない」とする労基法16条に違反する。

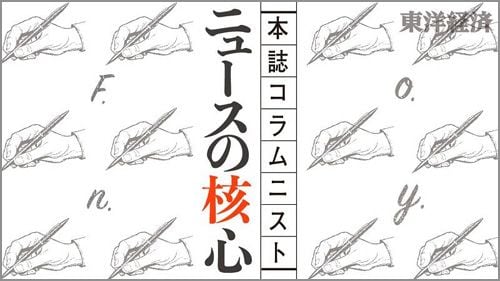



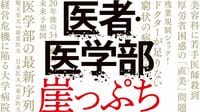



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら