がん専門病院では、治療が終わった患者は、次の患者のためにも早く退院して欲しい。2024年4月からは患者の平均在院日数を16日以内(2024年3月までは18日以内)にしなければ、最高額の入院基本料は請求できなくなっている。
Mさんは脳腫瘍が進行して歩けない状態だったのに、がん専門病院では、「とにかく早く退院してください」と退院を促された。
家族は自宅へ連れて帰ることも検討したが、同居している夫も70代で持病を抱えている。看護師でさえ怖がるような痰の吸引を頻繁にはできないし、もしも家に連れて帰ったら老々介護で共倒れになってしまう。
何とか入院させてもらえないかと家族が私のところへ相談に来たので、とりあえず当院に入院してもらい、リハビリをした。すると、流動食だが次第に食事がとれるようになって体重が増え、話もできるようになり、4月には車いすに乗って孫と一緒に花見に行けるようになった。
このように当院における慢性期の患者の治療とケアのスキルは、高度急性期を担う病院より上だと自負している。常に、時代の先を読み、慢性期の患者に最高の医療を提供しようとしてきた。
それでも、医療療養型と介護療養型の診療報酬点数は徐々に下げられ、中小病院の経営を維持できるような診療報酬は得られなくなった。父から受け継いだ借金の返済に追われ、経営は窮地に陥っていった。
経営難に陥っていく中小病院
中小病院には、地域の救急を担う急性期病院もあれば、当院のように、急性期治療が終わったけれどもまだ自宅に帰れる状態ではない慢性期の患者を受け入れている病院もある。
こういった中小病院が経営難に陥ってなくなれば、入院施設があって比較的簡単にアクセスできる医療機関がなくなることを意味する。
新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年夏にも、重症となった高齢者を受け入れてくれる中小病院がなかなか見つからない、大学病院や高度急性期病院を担う公的病院に感染した高齢者が集中して新たな重症患者を受け入れられないという事態に陥った。
それも、高度急性期病院の後方支援をする中小病院が経営難に陥ったり、減ったりしているからなのだ。
京浜病院は、医師会長の武見太郎氏と真っ向から対立しても国民皆保険制度創設を目指した祖父・熊谷千代丸が1940年に開設した興亜病院が前身で、戦後に京浜病院に改名した。私は3代目の病院経営者ということになる。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



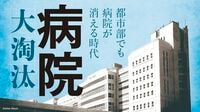




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら