
「いよいよ販売会社の選別が始まったということだ」。中部圏のあるホンダ系有力販売会社の幹部はそうつぶやいた。
ホンダが販売会社の再編に向けて着手したのがマージン制度の改革だ。2027年4月から登録車(一般乗用車)と軽自動車を合わせて年間3000台以上販売した販社に対し、マージンの一部を優遇する。さらに、高度な整備や修理の技術を持つ整備士を置いた「カーズテクニカルセンター」と呼ばれるサービス施設を置く販社や、中古車販売で優れた実績を持つ販社にもマージンを上乗せする。
ホンダならではの事情
こうした実績のある販社を優遇する背景には、ホンダならではの事情がある。4輪参入は国内メーカーで最後発。2輪事業が祖業のため、もともとは2輪販売を行ってきた1拠点しか持たない小規模販社を多く抱えている。歴史的に地場の名士がオーナーを務めているトヨタ自動車や日産自動車系の販社と異なり、ホンダ系販社は経営体力に乏しいのが実情だ。
今後は人口減少や若者の車離れなどが進み、「ますます新車を売りにくい環境になる」(東日本のトヨタ系有力販社社長)。電動化や自動運転技術、ソフトウェアサービスなど車両技術が高度化する中で、販売・整備の難易度も格段に上がると予想される。





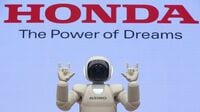



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら