何しろ、長期間入院しても医療費は無料なのだから、高齢者にとっては老人ホームなどの老人福祉施設に入るよりも金銭的に得だ。当時は、「親を施設に入れるなんて親不孝だ」という風潮もあり、家族にとっても病院に入院させたほうが世間体もよかった。
しかし、老人福祉施設の代わりに老人病院への社会的入院が増えたことが問題視されて、1983年には老人医療費の無料化は廃止された。
そして、老人病院の多くは、主に慢性疾患の高齢者を入院させる「特例許可老人病院」の基準を満たさなければならなくなった。この病院は医師と看護師の配置を減らして介護職員を多く配置する等の特例が認められた病院で、診療報酬は一般病院より低く設定された。
その10年後の1993年、厚生労働省は医療法を改正し、主に長期にわたって療養を必要とする患者の入院施設として「療養型病床群」を創設した。1998年には特例許可老人病院の新設はできなくなり、これらの病床はすべて療養型病床群への転換を迫られた。
このように厚生労働省は、診療報酬で突然新しい病床の区分を作ったり、一部の区分をなくしたりして、医療費を減らす方向へ病院を誘導しようとする。
「医療療養病床」と「介護療養病床」
2000年4月には介護保険法が施行されて介護保険制度がスタートし、2001年には医療法が改正されて療養病床が創設された。
介護保険ができたことで、高齢者向けの療養型病床群は、公的な医療保険で診療する「医療療養病床」と、介護保険で利用者にサービスを給付する「介護療養病床」に分けられるようになった。
利用する高齢者やその家族から見れば、同じような老人病院に見えたに違いない。それでも病院経営者は、この先も生き延びて職員を路頭に迷わせないためにはどちらが得か、診療報酬と介護報酬の改定や制度が変わる度に常に見極め、右往左往せざるを得ないのである。
高齢社会の到来を受け、医療療養病床と介護療養病床は増え続け、医療施設調査によると、2005年には一般病院の半分以上の4374病院が療養病床を有していた。
2006年には、国民医療費や介護給付費が膨張し続けていることを受けて、医療保険制度改革が断行され、2011年度末で介護療養病床が廃止されることが発表された。
結局、医療依存度の高い高齢者を受け入れる介護施設がなかなか増えなかったことから、期限が延長されたものの、2024年3月末で介護療養病床はすべて廃止された。介護療養病床の廃止は、制度を作っておいて、そこに病院が群がって医療費や介護保険給付費が膨張すると、その報酬を得られる項目を削除してはしごを外す代表的な例だ。
医療療養病床は残っているが、ここには、人工呼吸器を装着しているか、難病、重度の身体障害があるなどかなり重度な人しか入れない。
それ以外の人はかなり低い入院基本料しか取れないように診療報酬で設定されているので、病院側からみたらそういった患者の入院期間が長くなればなるほど赤字になる。だから、相当、医療の必要度の高い人しか入れず、治療が終わったらやはり退院を促すことになる。


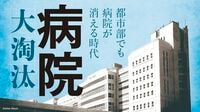




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら