しかし、治療の必要がないのに長期間入院している高齢者の社会的入院が問題になり、一般病床の長期入院患者に対する診療報酬が引き下げられたために、大学病院などで手術をした患者を受け入れ、長期入院患者が多かった2つの京浜病院の経営はいっきに苦しくなった。
京浜病院の院長だった父は、これまで受け持ってきた外科手術も継続し、一般病院のままにしたかったようだが、1985年に新京浜病院の院長になった私は、このままではどちらの病院も生き残れないと考えた。
その頃には平均寿命が延びて高齢化社会が進んできたこともあり、1993年にまずは新京浜病院を特例許可老人病院にした。
その翌年には、京浜病院も一般病床から医療療養病床にした。一般病床から療養病床へ転換し、高齢者をターゲットにした医療こそ、京浜病院と新京浜病院が生き残る道だと考えたのだ。
当時は、高齢者をベッドに縛りつけ寝たきりにして長期入院させ、金儲けをしている劣悪な老人病院があったのも事実だ。
高齢者へ質の高い医療の提供を
一方で、高齢者へ質の高い医療を提供しようとする老人病院もあり、その有志たちが「老人の専門医療を考える会」を結成して勉強会を開催し、この会から一般社団法人日本慢性期医療協会が結成された。
その勉強会に参加していた私は、京浜病院の未来は高齢者向けの慢性期医療にあると考え、高齢者を寝かせたきりにするのではなく、リハビリをしたり栄養管理を改善したりして最適な入院環境を整えようとした。認知症患者の治療とケアに力を入れ始めたのもこの頃からだ。
そして、介護保険制度の導入によって2001年に介護療養病床が創設されると、京浜病院と新京浜病院の両院を介護療養病床にした。
がん専門病院や大学病院のような大病院は、病気を治すための急性期医療は得意だが、手術などの治療や病気の後遺症が残った人や、治らずターミナル期に入った人、慢性疾患のある人のケアは苦手である場合が多い。
そこは、我々のような慢性期専門の病院の出番となる。
がん専門病院で「もうなすすべがない」と言われてやせ細って動けなくなり食事もできなくなった患者が、当院のケアで栄養状態が改善して口から食事ができるようになり、歩行や外出ができるようになったケースも枚挙にいとまがない。
ほかの病院ではお手上げで家族に暴言を吐いていた前頭側頭型認知症の患者が、当院の治療によって落ち着いたこともある。
例えば、2024年の3月、悪性脳腫瘍が進行した70代の女性・Mさんは、がん専門病院で容体が悪化して歩けなくなり、もともと50kg台だった体重が20kg台になってやせ細り、言葉も発せられない状態になった。痰の吸引が必要になったが、今にも呼吸が止まりそうになるので、がん専門病院の看護師もお手上げで処置も受けられなくなった。


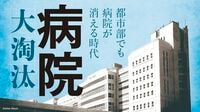




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら