憲法と教育の視点で見る「日本の教育」のねじれ 木村草太さんと内田良さんの対談から考える
木村:同じ構造は、教師と保護者の間にも当てはまります。モンスターペアレントという概念がありますが、これが問題含みなのは、「ハラスメント」か「正当なクレーム」かの認定権限が、教師側にあることです。正しい申し立てだったとしても、モンスターペアレントと言えてしまう。
他方で、モンスターペアレントに相当する教師を表す概念はあまり広がらない。ここには、保護者側からの不当要求は過大に受け取られる一方、教師側が正当な要求に対応しないことは過小に見積もられるという構図があると思います。
だから、学校にまつわる概念は、「教師には非常に大きな権限がある」という前提で組み立てないと、恐らくうまく機能しない。
教師の関与の「見える化」が必要
内田:学校における教師と子どもの関係には、「非対称性」があるんですよね。
例えば、教師が何らかの教育実践に取り組んで、子どもがこう変わりましたと説明するとします。その際に「子どもの変化」を強調しがちです。
実際には、見えないところで教師が相当な勉強や準備をして、子どもの変化につながっている。それにもかかわらず、教師が語る実践は、子どもたちがみずからの力で変わったように披露される。
というのも、教師はどうしても子どもを立てる傾向がある。子どもの頑張りを強調して、自分の関与を見えなくさせるんです。
それは子どもの成長にとってはメリットが多い一方で、教師が権力者として物事を動かしていることが不可視化されます。教育現場を考えるうえでは、教師の関与というものを冷静に見える化して、評価しないといけません。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

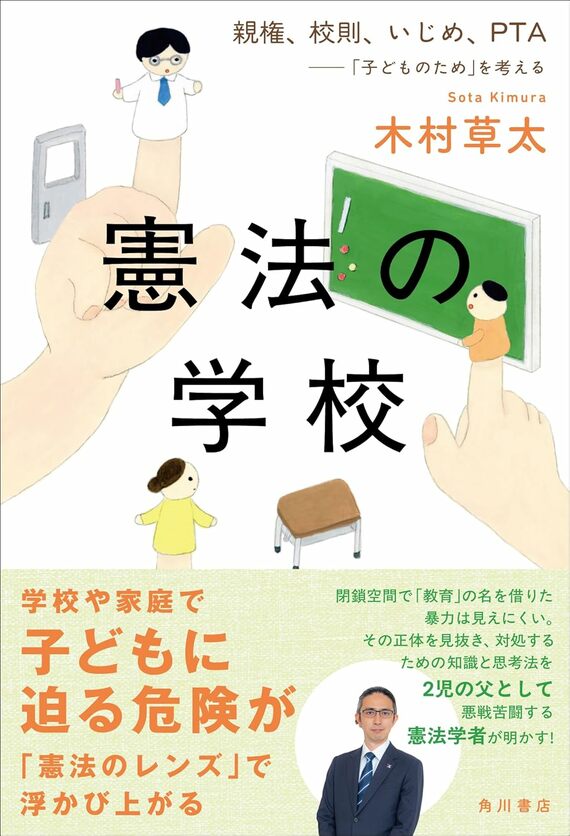































無料会員登録はこちら
ログインはこちら