ひどく患った病後の葵の上を心配し、左大臣も母宮も油断はできないと気を張っているので、それもそうだろうと光君は忍び歩きをすることもない。葵の上はまだ苦しげにしているので、光君はいつものように対面することもできずにいる。不吉なほどにうつくしい若君を、光君が今から心を尽くしてたいせつに世話する様子は、並大抵のものではない。ものごとがすべて思い通りになったような気がして、左大臣はしみじみありがたいと思う。葵の上の容体がすっかりよくならないことは気掛かりではあるが、あれほど重かった病気の名残なのだろうと考え、深く心配してはいなかった。
生まれたばかりの若君の目元の愛らしさは、藤壺(ふじつぼ)の生んだ東宮にひどく似ていて、光君はつい東宮を恋しく思い出してしまう。じっとしていることができず、参内(さんだい)しようと思い立つ。
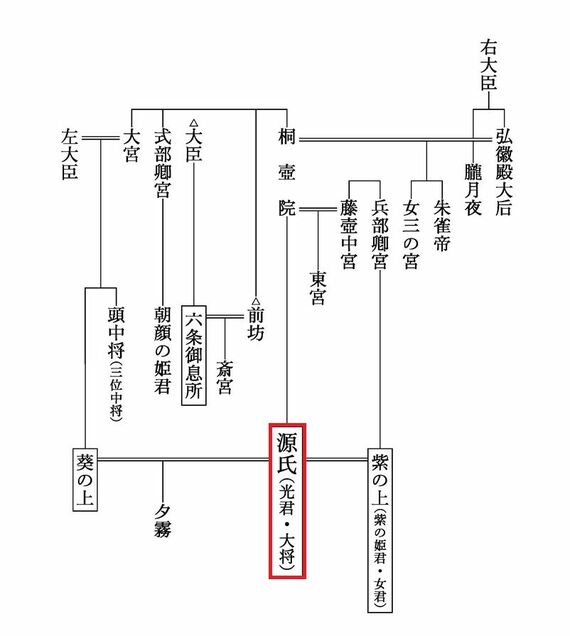
枕元に寄って声をかける
「宮中にずいぶん長いあいだ上がっていないので、気になっている。今日は久しぶりに外出することにします。その前にもう少し近くで話したい。これではご様子もわからなくて、あまりにも他人行儀でつれない仕打ちだよ」と恨み言を言うと、
「おっしゃる通りです」と女房は答える。「体裁を気になさるような間柄ではないのですから、ひどくおやつれになったとは申しましても、几帳越しのご対面なんてとんでもないことです」と、葵の上の寝所の近くに席を作る。光君は枕元に寄って声をかけた。葵の上は時々返事をするが、なおも弱々しい。けれども、もうすっかりだめだとあきらめた時の様子を思うと夢のようにも思えてくる。危篤に陥った時のことなどを光君は話して聞かせるが、あの息絶えたようだった彼女が、急に別人のようになってくどくどと話し出したことが思い出されて気持ちがふさぎ、「いや、もう、話したいことはたくさんあるのだけれど、まだ気だるそうだね」と言い、「お薬を飲んでください」と世話をはじめる。そんなことまでいつのまにお覚えになったのだろうと、女房たちは光君に感心しきりである。






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら