村上春樹『風の歌を聴け』が表現する日本的感性 「他人とは分かり合えない」から始まる人間関係
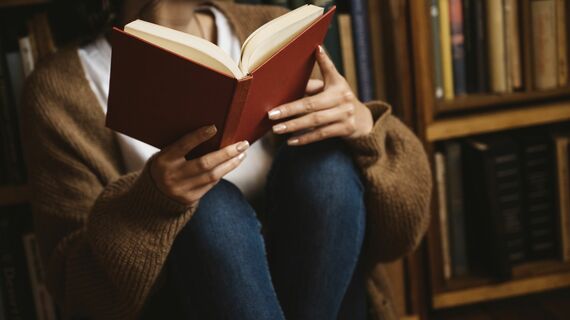
「葛藤」を回避する文学
浜崎:僕が春樹を読んだのって、中学から高校にかけてなんですが、その頃ってやっぱり思春期だから「葛藤」が多いですよね。その頃の僕は「いじめ」を受けて、勉強も学校も何もかも放棄していたんですが、でも、春樹のように「みんな分かり合えないよね」というふうには開き直る場所も、その余裕もなかった。なぜなら相手は、勝手に、こちらの心のなかに踏み込んでくるからです。そこでどう生きるのかというときに、僕は春樹の文学では心を支えることができなかった。つまり、他者が自分の心のなかに踏み込んできたり、自分が他者の心のなかに踏み込まなければならないときに生じる「葛藤」、その「葛藤」を強いられたときに、春樹のスタイリズムでは、自分の心を守れなかったということです。
例えば、そのときに支えとなったのは、この一連の文学座談会でやった作品でいえば、大岡昇平の『俘虜記』とか、大江健三郎の「セヴンティーン」の方です。つまり、生きるか死ぬかの絶体絶命の瞬間における人間の「生き方」、その「倫理」の在り方を描き出すのが文学なら、当時の僕には、春樹の作品は、現状肯定的に見えたということです。あえて言えば、春樹が描くのは、全て「葛藤の世界」ではなく、「葛藤の終わった後の世界」なんです。もちろん、これは、春樹論として見れば、完全に「ないものねだり」なんですけど(笑)。
藤井:確かに、彼が描くのはおおよそ「世界の終わり」ですね。

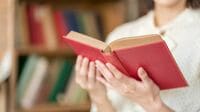































無料会員登録はこちら
ログインはこちら