村上春樹『風の歌を聴け』が表現する日本的感性 「他人とは分かり合えない」から始まる人間関係

柴山:他者の人格を尊重するという意味での倫理は、普通は深い人間的な関わり合いのなかでしか成立しないはずなんですけど、村上春樹の小説は「デタッチメント」の世界を前提に、それでも倫理的に人は生きられるとしたら何があるんだろうってことを問おうとしているような気がします。
それで思い出したのが、ジェイン・ジェイコブズという評論家が、ニューヨークの都市計画について書いた『大都市の死と生』です。昔読んで印象に残っているのは、優れた都市はどんなものかっていう問いの答えで、確か次のように書いていたんです。優れた都市とは、住民の誰かが旅行に行くときに、自分の家の前のお店に鍵を預けることができて、しかもその預けた主人がどこに行くかをいちいち聞いてこないような人間関係が成立している所だ、と。要するにお互いの存在を認めつつもプライベートには立ち入らない、微妙な信頼関係が成立している状態を、都市の理想だと考えたんです。村上春樹がここで書こうとしてるのも、そういう関係性ではないかと思ったんです。
絶望的な状況から始まる人間関係
藤井:ほんとにそうですよね。僕が村上春樹を読んだのは18くらいのときだったんですが、その前の12、3歳くらいのときから18になるくらいまでの間に、家族のことや学校のことでいろんな「葛藤」があったし、太宰治を読んでもう自殺しようと考えたこともあるし、なんだかよく分かんないからキリスト教に入信しようと思ったこともあるし、とにかく哲学を勉強しようとしたし、あるいはもうヤンキーの奴らと一緒に悪いことをしてるだけでいいやと思うこともあれば、いろんな恋愛もあったりだとか。たかだか17、8年間の人生ですけど、浜崎さんがおっしゃっているように、ローティーンからハイティーンにかけて僕も僕なりに「葛藤」してたわけです。
でも、ずっと15、6年、葛藤して、全てに敗北するんです。それで、その敗北のなかで、もう他者と「僕が望むレベル」で交流ができないことをだんだんと悟っていったわけです。だとしたら、交流できない前提で、そのなかで倫理的に正しく生きていく道を一応探るしかないじゃないか、だったらそうしよう、と思ったんです。そしてそう思えるきっかけは村上春樹の世界に触れたことだったし、そういうふうな生き方があるってことを、僕は村上春樹に初めて教えてもらったんだと思うんです。
浜崎:そうか、僕がちゃんと「敗北」してなかっただけなのかもしれない(笑)。
柴山:主人公の「僕」は昔の彼女が自殺してしまって、もう人と深く関わるのが嫌なんでしょうね。
藤井:でも、これは『ノルウェイの森』の話になってしまいますが、ものすごい助けようとしてるじゃないですか、自殺してしまう「直子」のことだって。指が4つしかない女の子のことも、できるだけ誠実に助けようとして、一晩抱っこして寝るんですよね。自分の体に女の子の鼻がくっついているのを感じながら。
だから現代っていうのは、ここからしかもう始まらないと思うんですよ。こんな絶望的な状況からしか。

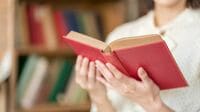





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら