大弐の乳母の子である惟光は、兄の阿闍梨(あじゃり)、乳母の娘と娘婿である三河守(みかわのかみ)などが集まっているところへ、折良く光君が立ち寄ってくれたことを心からよろこび、礼を言う。大弐の乳母も起き上がり、
「今さら惜しくもないこの身ではございますが、尼になるのをためらっておりましたのは、こうして以前と変わった姿をあなたさまにご覧に入れるのを残念に思っていたからでございます。出家して戒(かい)を受け、その御利益で生き返りまして、こうしてお見舞いにいらしてくださったお姿を拝見できましたから、今はもう阿弥陀仏(あみだほとけ)のお迎えも、心残りなくお待ち申せましょう」などと言い、さめざめと泣いている。
「近頃ご病気が思わしくないと聞いて、いつも心配しておりましたが、こうして世を捨てた尼のお姿になってしまったのは悲しいです。どうか長生きをして、私が出世するのを見届けてください。その後で、極楽浄土の最高位に、なんの差し障ることもなく生まれ変わってください。この世に少しでも執着が残るのは、よくないことだと聞いていますから」と、光君も涙ぐむ。
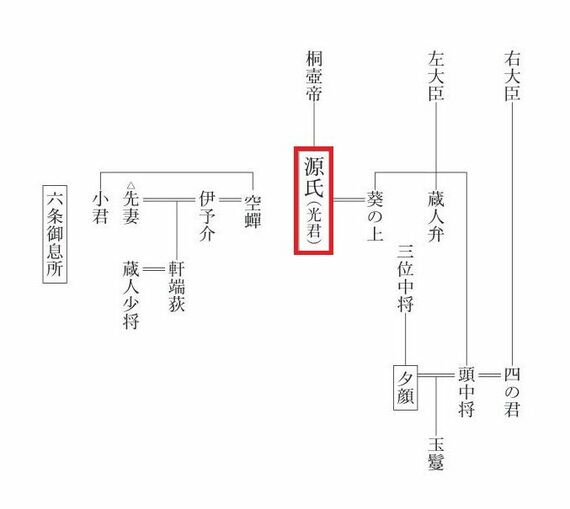
光君を育てた乳母の苦悩
乳母という、お世話する子ならだれでもだいじに思うような人は、どんなに不出来でも立派な子だと思いこむものだが、まして、相手は欠点のない光君である。お世話した自分の身も誇らしく思っていた乳母は、光君からそんな畏れ多い言葉をかけてもらい、ひとしきり涙に暮れた。子どもたちはそんな母親を見苦しく思い、
「いったん捨てたこの世にまだ未練があるように、泣き顔を隠しもせずお目に掛けていらっしゃる」と、つつき合い、目配せをし合っている。光君は乳母をしみじみいとおしく思い、
「私がまだ幼い頃、かわいがってくれるはずの母も祖母も亡くなってしまって、世話をしてくれる人はたくさんいたようですが、私が心から親しく思える人はあなただけでした。大人になってからは、子どもの頃のように、朝に夕にとそうしょっちゅう顔を合わせることもできず、思うように訪れることもできませんでしたが、やっぱりずっと会えないでいると、心細くなります。もうこのままずっと会えないなんてことがありませんようにと、願っています」
と、心をこめて話しながら袖で涙を拭う。その袖の香りが部屋いっぱいに満ちている。母を見苦しいと思った子どもたちも、なるほどいかにも考えてみれば、光君を育てたこの母は並々ならぬ幸運な人なのだと思い、もらい泣きをするのだった。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら