遠藤 しかし最近、ChatGPTが画像を読み取れるようになったんですね。そこで、この画像を英語で説明してくださいと入力してみたところ、すぐに答えが返ってきました。
AIという技術があれば、小学生でも東大の入試問題を解けるようになったということです。思考力、判断力、表現力こそが、AIの得意分野になりつつあります。
そういう技術がある時代に、この問題を独力で解くために、小中高の12年間も学習を続ける意味とは何だろうと考えてしまいます。
これから必要だと言われていた資質もそうだし、人間にしかできないと言われていたことも、この先すべてAIのほうがうまくできるようになるかもしれない。
こうなると、AIができないことを人間がやるという発想ではなく、AIより人間のほうが得意なものなどない、という前提で、それでも人間としてどう生きていくかを考えなくてはいけないと感じています。
あえてよくない選択肢を選べるか
宮田 私は、そのカギは主体性にあると思っています。
人は自ら目的を持ったり、よりよく生きたいと思ったときに、さまざまな課題が見えてくるものです。最初は自分の課題かもしれませんが、それがだんだん外に広がって、地域の課題とか、もっと大きな課題の解決につながっていく。
となると、より自然に、主体的でいられるための経験やマインドセットを持つことが大事かと思います。
遠藤 おっしゃるとおりです。病気になったときに、あなたはこの薬を飲むのがいいとか、地球に対してもあなたにとっても優しい行動はこれだといった「正解」は、機械が提示してくれるようになる。
そこで、主体的でいられるかというのは、あえてよくない選択肢を選べるか、というのが、人類の分かれ目になるのかなと思います。
宮田 主体性を育むために行政や学校がやるべきことはなんでしょうか。
遠藤 人や機械から言われたことをやるのではなくて、自分で決めていくという練習を常にやっていくことでしょう。それは学校だけでなく、家庭とか、社会とか、いろいろな場でそうするということです。
外食したときに、何も言わなくても「いつものもの」が出てくることをかっこいいと思うかどうか。
今までの日本の価値観とは違うかもしれませんが、某サンドイッチチェーン店のように、パンはどれにするか、レタスは必要か、トマトはどうか、ドレッシングは何にするか、飲み物は、という具合に、いちいち意見を求められるという経験が、ある程度必要だと思います。
(第3回に続く)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



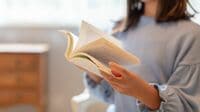




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら