日本の場合、企業だけでなく、社会全体が大学院生に対する理解に乏しいとも言える。松田さんは「社会に対しても、文科系に限らずだが大学院生の地位向上については今以上に働きかけていく必要がある」と話している。
複数の調査結果から、大学院生を取り巻く環境の厳しさが伝わってくる。博士課程に進学し、修了した場合は、研究者の道に進んで大学への就職を目指す人も多い。しかし、前述の通り正規採用の教員になる道は険しい。
研究者の「使い捨て」も問題に
最近は研究者の「使い捨て」も問題になっている。非常勤講師については5年、研究者については10年を超えて勤務することで、無期雇用に転換できる権利を得られることが法律で定められている。にもかかわらず、大学によっては5年や10年を迎える前に雇い止めされる事態が起きているのだ。
また、大学院生が抱える悩みに、パワーハラスメントやアカデミックハラスメントがある。上下関係が絶対で、閉鎖された空間とも言える大学の研究室では、ハラスメントが起きやすいとされている。
ハラスメントを行った教授に対して懲戒処分が下されていることは、全国の大学で頻繁に報道もされている。それでも、ハラスメントを公表していない大学が多いため、実態がわからないのが現状だ。
さらに、ハラスメントの被害に遭って大学の窓口に相談しても、適切に調査が行われないことも多い。「全国院生生活実態調査」でも、次のような声が寄せられている。
このように、大学院生は研究活動にも、将来にも大きな不安を抱えている。研究力の強化を掲げる国の政策は、大学院生が抱える不安を解消し、減少傾向にある大学院生を増やし、多くの研究者を育てることにつながるのか。大学院生1人ひとりに話を聞きながら、問題点を探っていきたい。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



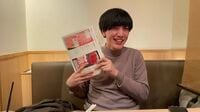



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら