源頼朝が征夷大将軍に実は大して関心なかった訳 役職が偉いのではなく、偉い人が重役になる出世
「覇王とは?」と思うところですが、貴族は中国の古典をよく読んでいますから、その世界観にもとづいて義教を説得しようとするわけです。中国の春秋時代には覇を唱える人物、覇王がいた。ここは「幕府の将軍に対抗できるほど強い力を持った人物」と捉えておけばいいのですが、そうした人物が現れて勝手に政治を始めてしまったら、そのとき義教は、何と言ってその人物を否定するのか。
もし征夷大将軍に任命されていれば「おまえは征夷大将軍に任命されていないが、自分はされている。だから政治を行うことができるが、おまえはできない」と、自分の正統性を主張することができる。
「だからあなたはきちんと手順を踏んで、征夷大将軍になってから政治を始めてください。征夷大将軍になるためにはそれなりの時間が必要ですが、それまでは政治にタッチしてはいけません」と朝廷は言うわけです。これに対して義教は「そんな悠長なことを言ってられるか」と、坊主頭を布でつつんで政治を始めてしまいました。
朝廷はポストを与える存在として生き延びていた
鎌倉幕府の頼家の場合は、仲間たちが「2代目は頼家さんだ」と認めたら、それでよかった。征夷大将軍であろうが何であろうが関係なく、政治をやっていい。トップとして振る舞っていいということになった。
同じように足利義教も、室町幕府を構成する人々が「俺たちの次のトップは義教さんだ」と認識し、その認識を共有していれば、義教はそれだけでトップとして振る舞ってよかった。戦争が起これば大将として出陣するし、リーダーとして政治をやっていいのです。
朝廷は「いやいやいや。朝廷が出すポストは大事ですよ」と言うわけですが、それは当然で、朝廷側にしてみれば「自分たちが与えるものは、あなたにとってものすごく大事です」と言いたい。それだけ、自分たちの存在もまた大事ということになりますから、これは当然のことです。しかし結局、義教はポストなどに構わず、頭を包んで政治を始めてしまう。この辺りから朝廷の力は完全に下降線で、武士の力が朝廷をはるかに凌駕するという形になったと言えると思います。
逆に言えば、朝廷はポストを与える存在として生き延びていたわけです。錦の御旗を出す存在として存続していたということが、義教の将軍就任のときのごたごたでよくわかります。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

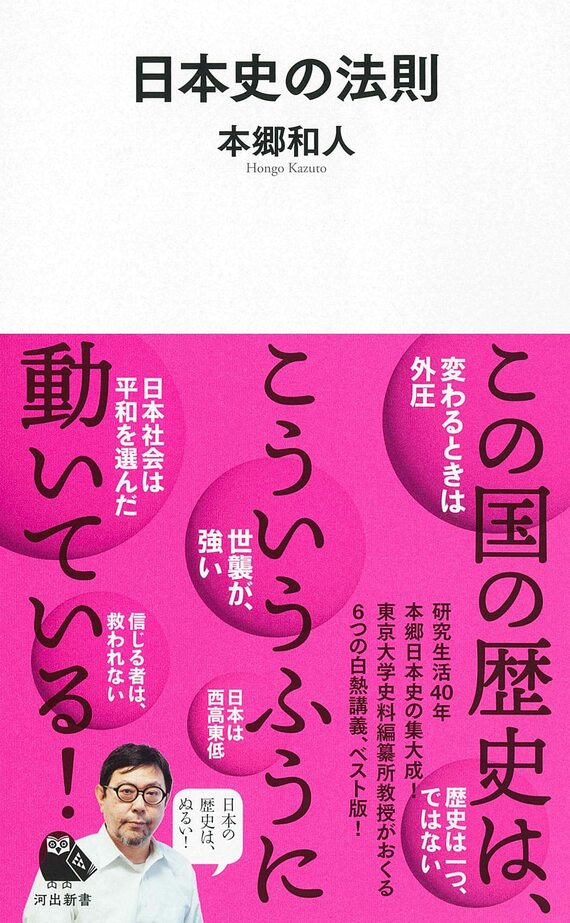
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら