北海道のTVマンが記した「デス・ゾーン」の真意 開高健ノンフィクション賞・河野啓氏に聞く
――登山家たちからは「パフォーマンスがすぎる」「登山家ではなく、登山をやっている人間」「欽ちゃん球団みたい」などと評されていたそうですが、資金面も含め、栗城さんには熱心な支援者が多かった。その人たちの中にも、彼の変貌を指摘する人がいる。これは、河野さんがテレビメディアの人だからこそ聞きたいんですが、意図はともかく、テレビが取り上げることで人は変貌してしまう。その怖さを感じたことはありますか。
栗城さんの場合、最初の頃はさっき言ったように街中でもリュックを背負っていた。それがトレードマークだったんですが、取材を始めて2年目、エベレストに挑戦するスケジュールが出た頃には必ずキャップを被り、キラキラと反射するサングラスをかけるようになっていた。そのとき僕は、ヤンキー先生(義家弘介氏・現衆議院議員)のことを思い出したんです。
彼も番組(河野さんがディレクターを務めた、高校中退者や不登校の生徒を受け入れる北星余市高校を取材したシリーズ)でブレイクしてくると、金色のペンダントをするようになった。そのほうが周りも喜ぶだろうというサービス精神でもあったったんでしょうけど。とくにテレビの仕事をしていると、取材をされることで外見が変わっていくということは感じますね。
ヤンキー先生のことを思い出した
――栗城さんを知る人たちと対面し、ときに取材拒否にあう中、終盤が非常に印象的でした。栗城さんが頼った占い師を探しだし、会いにいく。インタビューの問答から謎が氷解していくところがあるとともに、栗城さんの存在がいとおしくなる。取材の最後が占い師になったのは意図されたことですか。
取材をしながら、これは劇場っぽい話だなと思うようになっていました。まず、占い師さんの取材が最後になったのは山仲間や幼なじみといった、すぐにたどれる人ではなかった。特定なんかできっこないだろうと諦めていたんですが、やるだけやってみようか。ネット情報から彼なら誰に頼むだろうか。20人ほどに絞り込んで、片っ端からメールと手紙を送り、返信があったのが本に出てくるX師だった。
この本をどう捉えるか。それは読者に委ねたいんですが、取材をしていて「単独」という言葉が浮かんできたんです。彼のキャッチコピーでもあった「単独、無酸素」の単独なんですが。X師の取材をとおして、それは山岳用語の単独ではない、ちがう重みをもって響いてきました。
栗城さんはいつも「夢は叶う」「夢の共有」を訴えかけていたけれども、重要な局面では「ひとりぼっち」だった。常に自分を律しながら生きていかなければいけなかった。しかし、それは彼だけでない。僕も、いや誰もがそうで。その「単独」を目指せない人間がネットに群がって、人を叩いているというイメージを同時にもったんです。



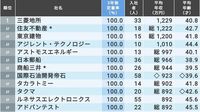



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら