北海道のTVマンが記した「デス・ゾーン」の真意 開高健ノンフィクション賞・河野啓氏に聞く
――丁寧に数多くの人に話を聞くために訪ね歩いておられます。当人が亡くなっている以上それ以外に方法はなかったのでしょうけど、取材のブランクが10年もあっただけに大変だったのではないですか。
たしかに。縁が切れてからは、たまにテレビで目にすることはあっても心は動かなくなっていました。なぜ心が離れたかという理由は本の中に書いたとおりなんですが。大事な約束を反故にする。こんなやつ、もう追っても仕方ない。頭の中からスッパリ削除してしまった。だから、またデータを取り出すことになろうとは思わなかったですね。
しかし大変ではありましたが、彼が僕と別れたあと、どのような人生を歩んだのか知りたいという気持ちが上回った。それと、これは偶然なんですが、彼が亡くなった翌月からブログを始めたんです。仕事の裏話のようなことだったんですが、熱心な読者は母親ひとりだけ。登録者は10人もなかったのが、ふと栗城さんのことを書きたくなった。そうしたらアクセス数が1万に跳ね上がったんです。その驚きもありました。
表現の面ではとてもストイックな人間だった
――本を読んでいて、河野さんと栗城さんに似通ったものを感じとりました。たとえば、お母さんが亡くられたとたん河野さんはブログを更新する意欲を失ったとつづられていて、いっぽう栗城さんは「カメラがなければ、エベレストには行かない」と語っている。
大勢の観客を強く意識した登山と、たった一人の読者に向けた違いはあるにしても、ある意味符合するというか。栗城さんは「夢の共有」という言葉をよく使われていたそうですが、誰かに見られていることを意識することで人は前に進むことができる。それは誰しもに当てはまることだと思いますが。
私と母の関係でいうと、50代の息子と80代の母親との間に会話は成り立たないんですよね。すくなくともウチの場合は。母が死んだあとにあらためて感じたことですが、母が本当に喜んで読んでくれていて、僕と母との会話ツールとしては役立った。
では、栗城さんはいったい誰を意識して山に登っていたのか。誰かのために登っていたのは確実だったと思います。そうでないと、あんなに登山の力量が未熟な人が、たとえシェルパの助けを借りたとはいえエベレストには行けなかったでしょう。
――人物取材をする場合、対象に対する「共感」が欠かせないと思うのですが、栗城さんの負の一面を描写しながらも文章から愛情のようなものを感じました。彼と自分に類似するものを感じることはありましたか。
そうですね。まず似てないのは、ぜったい僕は自分の泣き顔にカメラを向けることはしない。どんなにそれがウケると計算できたとしても、それはできない。それで、質問は似ている部分ですよね。
表現者として、どうすれぱ人が喜んでくれるか。そのために自分は何をしないといけないかを彼は常に問い続け、自分に対して、表現の面に関しては、とてもストイックな人間だった。僕のことはさておき、彼は仕事に対しては真摯だったとは思いますね。



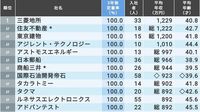





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら