北海道のTVマンが記した「デス・ゾーン」の真意 開高健ノンフィクション賞・河野啓氏に聞く
栗城史多はこういう登山家で、専門家の中にはこういう評価もあるけれども魅力のある男だという出し方ならまだしも、ただただ群がってうたいあげてしまった。彼がスポーツクライミングをやっているような人だったら別だったんでしょうが、「死の地点」に向かう人間をバラエティー目線で追うというのは明らかに間違っていた。いまさらですが、彼と仲たがいした後の、指を失くしてからの彼を撮りたかったと思います。痛切に。どんな思いで登ったのか。とくに、貶されるようになってからの彼を。
――後退戦の最中の彼を追うことで、見えてくるものがあったかもしれないということでしょうか。
それはわからない。ただ、彼が栄光を失い、叩かれる存在になって何を学んだのか。叩かれながらもなお、なぜ山に登るのか。自分の中で彼がどのように整理し、登っているのか。占い師さんの証言はありますが、実際に彼から直接聞いてみたかったですね。
先日、登山ライターの方と対談させてもらったんですが、私が取材した2008、2009年頃の写真をお持ちになられた。その人は、2016年に取材で栗城さんと会われたそうですが、「僕が会った栗城さんはこんなに生き生きした表情はしていなかった」とおっしゃられたんです。
縁を切ってしまった。そのときの僕の心の動きとしては自然なことだったんですが。凍傷で指を切断したことを知ってはいたので、メールのひとつでも送って彼と付き合いを再開していたら、いろいろ発見はあっただろう。それは非常に心残りです。
最初に考えたタイトルが「エベレスト劇場」
――本を読んで感じましたが、河野さんの取材の基本スタイルは対象と距離をつめながら緊密に取材するというものなのでしょうか。
人物ドキュメントの場合はそうですが、ある程度、距離を保つようにはしています。たとえば「栗城クン」とは呼びかけたりはしない。彼は親し気にクンと呼ばれるのを好むタイプですが、僕はずっと「栗城さん」でした。
――なるほど。逆に「クン」と呼びかけたほうが、懐に踏み入れそうなイメージがありますが。
人にもよると思うんです。これは僕の性格にもよるのかもしれないですね。彼は20歳くらい下でしたが、「単独無酸素で世界七大陸を登頂を目指している、すごい人だ」と思って取材していたというのもあったからかもしれませんね。
――最後に、副題にある「エベレスト劇場」の真意をうかがっていいですか。
最初に考えていたタイトルが「エベレスト劇場」だったんですね。彼はエベレストという舞台を展開した演出家であり、役者でもある。エベレストを劇場にした男というのが彼を最も言い表していると思ったもので、その言葉は入れたいと思っていました。彼も、自分の登山は「作品」だ、自己表現だということは繰り返し口にしていましたから。
栗城さんは、多くの人に夢を持ち続けることの大切さを力説して死んでしまったけれども、人間は夢破れたところから新しい自分を発見したり、新しい生き方を模索できたり、夢は破れることのほうに意味がある。私はそう思うほうで。これはネットに書かれていた栗城評ですが「栗城さんは売れないロック歌手のようだ」って。うまいこというなぁと思ったんだけど、夢敗れたところから一歩を踏み出す。テレビ屋としては、そういう栗城さんを撮りたかったですね。
(文中一部敬称略)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



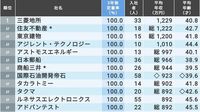



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら