財力がある家庭の子ほど「東大」に進学する現実 大学受験ではずっと「公平さ」が問われてきた
一昔前の日本であれば、学費は高くなかった。たとえば筆者が大学に入学した1967年当時、国立大学の授業料は年1万2000円にすぎず、学費そのものの壁はそこまで高くなかった。
そして今では授業料はもちろん、かかる生活費も高くなり、進学先が国立大学であろうと、奨学金を受けようと、極度の貧困家庭において子弟を大学進学させるのは困難となった。一方で豊かな家庭ほど、レベルの高い大学への進学を果たせるのがあたり前になりつつある。
2020年初頭からの新型コロナウイルスの広がりにより、アルバイトの口が減るなどし、「大学生活をあきらめる」という判断を下す学生が出てきていることが新聞などを通じて報道されている。
文部科学省は慌てて2020年4月から奨学支援制度を拡充。授業料減免や返済不要の奨学金を拡大することを発表したが、これなども教育の機会不平等、あるいは不公平にまつわる話題だろう。
ただ大学進学に先立って、名門・有名大学への進学を目指すなら、今や高校どころか、小中学校の時から準備せねばならない。そして水準の高い学校へ進学するには、普段から塾に通ったり、家庭教師についてもらったりする必要も生じてくる。
しかし学校外教育に資金を出せるのは、当然だが、家計が豊かな家庭に限られてしまう。
東大生の高すぎる世帯年収
たとえば、東京大学在校生の家庭環境について調べた「2018年学生生活実態調査の結果」では、その世帯年収について「950万円以上」が60.8%にまで達し、メディアを通じて話題になっていたのは記憶に新しいところだ。
ちなみに「平成30年国民生活基礎調査の概況」(厚生労働省)によれば、2017年の日本全体の平均世帯年収は551.6万円。単純に比較はできないものの、東京大学合格者を輩出した家の多くが、日本の平均世帯年収よりずっと高い所得である、ということは言えるだろう。
つまり、今の日本での「教育の機会不平等」「不公平」とは、そのまま家計の経済的豊かさに帰因していることが分かる。このような中で、もともとの「教育の機会平等」という言葉が持っていた意味は、すっかり変容したと言わざるをえない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

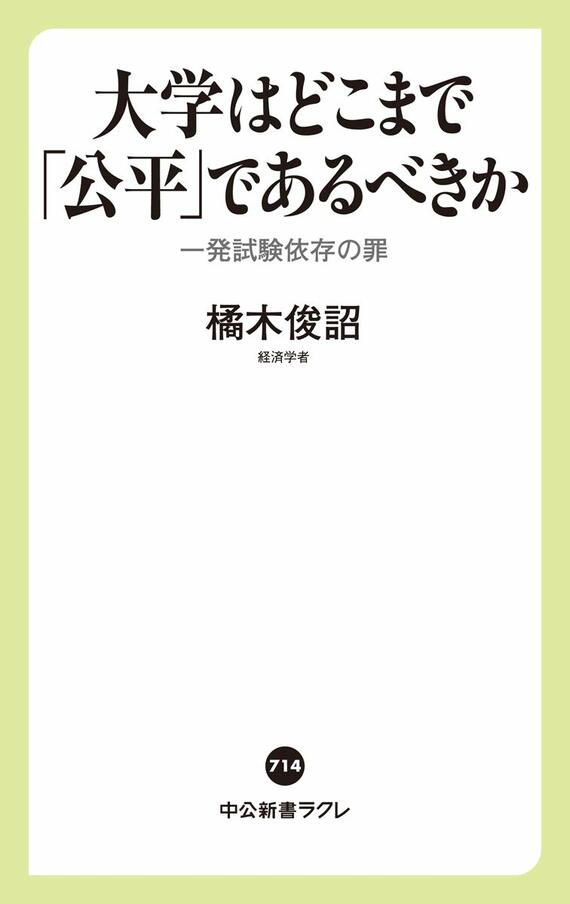































無料会員登録はこちら
ログインはこちら