「あのとき、北海道は社会全体が緊迫した空気に包まれました」。馬詰さんは振り返る。
「私は、ハイリスク妊婦さんも多かった、ここの産科を何としても守らなければと思いました。妊婦健診の実施主体である道庁に相談したところ、どさんこプロジェクトに関わった部署がスピーディーに動いてくれたのです。行政にも大学にも支えられ、皆が同じ方向を向いたので大きなエネルギーが出ました」
計画からオンライン妊婦健診がスタートを切るまでの日数は、わずか8日間程度だった。妊婦たちも通院や待ち時間が不安だったので、外来で勧めるとほとんどの人が歓迎した。
4月初めまでに延べ70回のオンライン妊婦健診が行われ、そのうちの1回で妊婦本人が気づいていない陣痛が発見され、切迫早産の治療を早期に開始できた。

「やってみて、オンライン診療にはいいことがたくさんあるとわかりました。もし妊娠中の女性医師がいたら、今の時期はオンライン診療に専念してもらってもいいかもしれませんし」
もちろん、産科には血液検査など自宅ではできない検査も多く、馬詰さんは「妊娠24週以前の超音波検査はとても重要」だという。
だから、あくまでも「対面診療とうまく組み合わせることが前提」で、その時々のリスクと恩恵を天秤にかけることが必要としつつ、オンライン妊婦健診にはこれまでの医療にはないさまざまな可能性があると馬詰さんは感じていた。
ネックは導入費用
ネックは、導入費用だ。小型胎児モニターは、まだ生産台数がとても少ないこともあって高価だ。さまざまな可能性を秘め、ハイリスク妊娠においては医療費を抑制する可能性もあるが、その公益性を理解する先進的な都道府県はまだ少ない。
しかしながら今春、これまでにない動きが起きた。4月末、日本産婦人科医会はメロディ・インターナショナル社の機材提供を受け、小型胎児モニターを用いた遠隔医療の実証実験を全国13の医療機関で開始した。
参加したのは大都市圏や地方都市の施設だ。遠隔医療プロジェクト委員会の平田善康さん(平田クリニック院長)は同会の会報で「遠隔医療はすでにマスト」「情報通信機器は完成」と記し、「システムづくりと実証実験、それに見合った報酬の獲得」が必要とした。第二波が来た時には、各地の都市で妊婦健診が選べるようになっていることを期待したい。
病院という一見不落に見える砦も、災害や感染でいつ何時どうなるかわからないことを、私たちはもうよく知っている。遠隔医療は、現代では過疎地でも、都市でも、等しく基礎的なインフラではないか。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



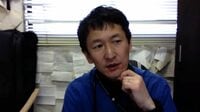






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら