
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は第一波が引いてきたものの長期戦を覚悟しなければならない。妊娠中の女性たちの不安は当分の間続くだろう。だが、この第一波を振り返ると、医療機関のオンライン診療は特例的な規制緩和が4月に認められたが、妊婦が月に1回、産み月が近づくと1~2週に1回という頻度で産婦人科へと通院しなければならない「妊婦健診」は、オンラインで受けられるところが、まだほとんどない。

妊婦のオンライン診療には実は20余年もの歴史がすでにある。ただ、コストや無関心など社会的な理由がブレーキになって、「あれは医療過疎の地域や離島のもの」とされてきた。かくして都市の妊婦たちはその技術を知る由もなく、今日も院内感染のニュースに怯えながら通院している。
ふたつの命を守り、未来がここにかかっている妊婦の医療が、ニューノーマルから取り残されてはいけない。
何が妊婦健診のオンライン化のネックとなり、それにどう対応してきたのか。医療過疎地域や離島ではどんな取り組みがなされてきたのか。ここへきて、都市部においても必要性が認められてきたオンライン妊婦健診の歴史を振り返りつつ、メリットと課題を整理しておきたい。
専用機器も小型化が進んでいる
もともと妊婦の診察をオンライン化するのが難しかった理由の1つは、胎児の健康を調べる超音波検査や「胎児モニター(分娩監視装置)」など、診察に機械が必要なことだった。胎児モニターは、胎児心拍数と子宮の収縮具合(陣痛)の両方を心電図のように連続時に計り、胎児の元気さやお腹の張りを読み取れる「胎児心拍数陣痛図(Cardiotocogram :CTG)」を描く。
ただ、超音波検査は医学的には毎回実施しなくてもいい。胎児モニターについても、2000年前後からデータ送信機能がついた小型の機械ができ始めた。その試作機は、皇后雅子さまの妊娠管理にも使われている。
2018年には、スマホ程度の重さしかなく、妊婦自身が簡単に装着できる、超小型のIoT胎児モニター(販売名「分娩監視装置 iCTG」)が登場した。片手に収まるスピーカー付きトランスデューサーをお腹に当て、「トク、トク、トク」と心音が聞こえる位置を探し当てたらベルトで固定するだけだ。
検出データはBluetoothでスマホなどにワイヤレスで飛び、クラウドを経由し、リアルタイムで医師のタブレットやスマートフォンに送信される。
胎児モニターをこのように進化させてきたのは、1970年代、東京大学在籍中に胎児モニターの基本原理を世界に発信した1人、産婦人科医の原量宏さん(現・香川大学名誉教授)だ。



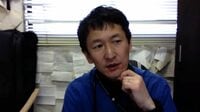






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら