
職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)とは、職務上の地位や人間関係など職場内の優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超え、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為のこと。「精神的な攻撃」「身体的な攻撃」「過大な要求」「過小な要求」「人間関係からの切り離し」「個の侵害」の6類型に分けられる。
人格を否定するような言動を行う、同僚の目の前で叱責する、他の職員も宛先に含めたメールで罵倒する、必要以上に長時間・繰り返し執拗に叱るなど、精神的な攻撃に類するものがとくに多い。上司と部下のコミュニケーションの過程で起きやすく、事案化も増えている。
法制化で企業の対応に変化
背景として、2020年にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行されたことが大きい。具体策を掲げたり、社内外に相談窓口を置いたりするなど積極的に動いている。相談窓口に寄せられる件数は増加しており、ハラスメント問題が顕在化しやすくなったのはポジティブな効果だ。

一方、ハラスメント窓口に相談すると関係者に対する事案調査を経て認否に至るが、ハラスメント認定されない事案も多くある。管理職や上司からの指導をハラスメントと捉え、相談するケースが一定数あるからだ。

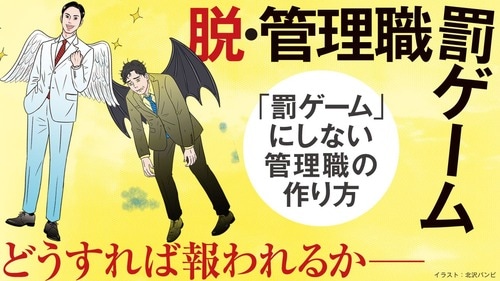


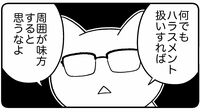





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら