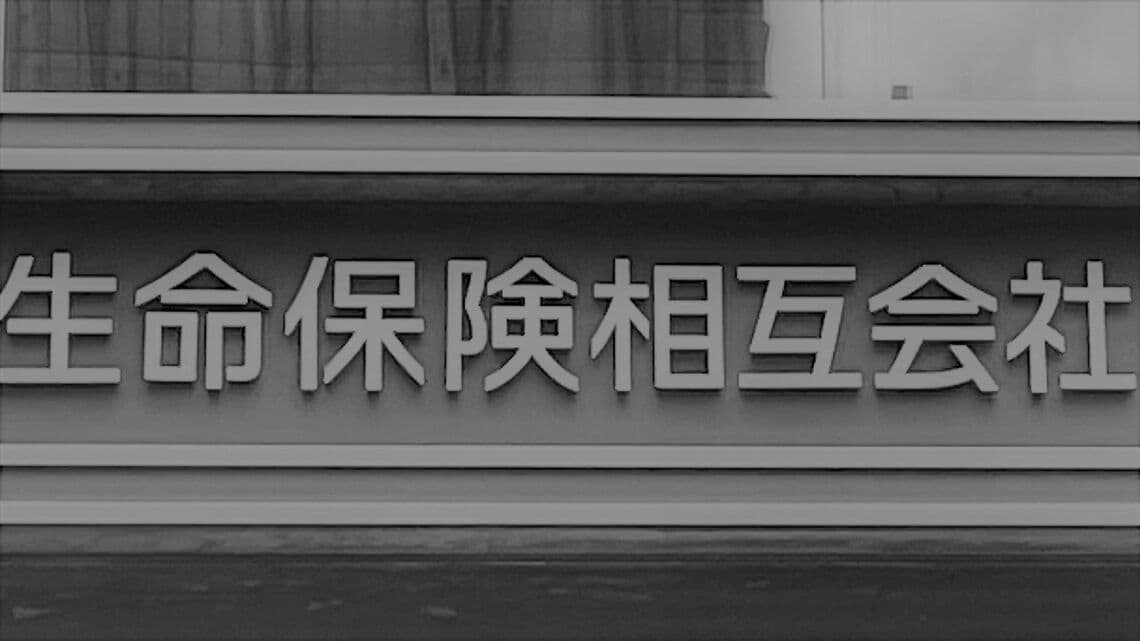
「買い手不在」――。5月21日、新発30年物国債の利回りが一時3.185%まで上昇(価格は下落)し、ほぼ四半世紀ぶりに過去最高を更新した。残存期間が10年を超える超長期債市場では、低調な売買と需要の減退を懸念する声が機関投資家から多く聞かれるようになっている。
中でも買いが鈍っていると指摘されているのが、同市場の主要な市場参加者である生命保険会社だ。需給の構造を探る上で、まずは生保における財務のカラクリについて丁寧にひも解いていこう。
積極買い入れの背景に新規制
そもそも生保は、終身保険をはじめとして20年や30年といった期間の長い契約を、貸借対照表の「負債」側に多く抱えている。一方で「資産」側では、同じように期間の長い20年物国債や30年物国債などを購入・運用することで、保険金や解約返戻金の支払いに備えているわけだ。
生保各社の財務資料を見ると、保険契約などの負債側と、保有債券などの資産側のデュレーション(平均残存期間)が、それぞれ10年前後という会社が多いことが分かる。負債と資産のデュレーションギャップ(年限差)は、かつて10年を大きく超えていたが、2024年度末時点では大手生保を中心におおむね1年前後まで縮小させている。
日本生命保険で運用部門を担う佐藤和夫専務執行役員は、これまで超長期債をほかの生保と比べてもかなり積極的に買い入れてきたといい、結果として「デュレーションギャップは足元でほぼゼロの状態にある」と話す。
多くの生保がデュレーションギャップを急速に縮小させた背景にあるのが、2025年度から導入されるESR(経済価値ベースのソルベンシー比率)という新たな国際資本規制だ。
新規制では、負債と資産のデュレーションギャップが大きいほど、金利変動時のリスクが高く判定され、財務の健全性評価が低くなってしまう。そのため生保各社は、資産側のデュレーションをより長くしてギャップを縮小しようと、30年物などの超長期債をここ数年、積極的に購入してきた経緯がある。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら