「話を聞いてくれるとわかれば、患者さんはいろんなことを話してくれるものです。仕事の話やご家族のこと、これまでの人生でいちばん輝いていたときの話をされる方も多いですよ。僕はただ、好奇心を持ってお話を聞いていきます。30分の診療時間では足りず、次回に持ち越すことも。
やがて、どのような緩和ケアを求めているのか、自宅に帰りたいのか、体だけでなく心の痛みはどうか、なども見えてきます。ご家族も、本人に改まって聞かなくても、横に座って聞くことで冷静に本人の意思を確認できます。本人が話し始めたときに聞く。それが本当の話し合いだと思っています」
「人生会議」には第三者が必要
緩和ケア医は“司会役”のようなものだと新城氏は言う。患者・家族・医師のどこかに対立構造をつくらず、誰か一人だけが多く話さないように気を配る。
「診察室ではテーブルを挟んで、三角形に座ります。みんなが同じくらい話せるのが大切。医療やケアについて家族が話しすぎているようなら、『こう言っているけど、あなたは同じ考えですか?』と患者さんに話を振る。向こう対こっちという雰囲気をつくらず、誰か一人が大切なことを決めるのではなく、みんなで決めたという形になるよう気をつけています」
新城氏は、人生の最終段階における家族の話し合いには、緩和ケア医のような第三者が必要だと痛感している。病気が進行し、患者本人の意思表明が難しくなってからはなおさらだ。
「家族だけで、死をどう迎えるかという深刻な話をするのは、苦しいことですよね。親と子、家族の中には、『死について話す』というチャンネルがそもそも備わっていないのではないでしょうか。もちろん上手に当事者の希望を聞き出して、話し合いができるご家族ならいいかもしれません。
でも、たいていは、家族の中で誰か意見が強く熱心な人が、治療方針を決断するだけになりがちです。家族であっても、誰かの人生の最期を背負うのは重すぎる」
「だからやはり緩和ケア医のように、すでに患者と『死について話す』チャンネルがある医療関係者が間を取り持つべきだと考えています。誰か一人に責任がいかないように、医師が、『それが最善の選択です。それを患者さんは望まれていますね』と承認してこそ、家族は『これで良かったんだ』と納得して見送ることができるのだと自覚しています」



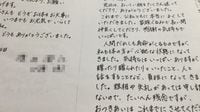



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら