3択とは、自宅で最期まで過ごすか、ホスピスに行くか、地元で通院できる病院を探すか。近隣のホスピスや病院のリストを渡されることもあるが、たいていは、行き先は病院側に決められてしまう。在宅介護の具体的な支援活用の説明はほとんどない。突然の宣告に患者や家族は途方にくれる。その中で、緊急時の心肺蘇生行為、人工呼吸器や胃瘻(いろう)の設置をするかどうか――延命治療をするかどうかを問われる。
「患者や家族は、治療の施しようがないと言われショックを受けている状態で、急いでこの重大な事柄を決めなくてはいけない。しかも、主治医がじっくりと患者や家族の人となりや状況を判断して、一緒に考える余裕はほとんどありません。
僕がかつて勤めていたホスピスでは、病院からの紹介状を持ってくる患者さんがほとんどでした。自ら希望して『私はホスピスで最期を過ごしたい』などと意思を固めていらっしゃる方はごくまれですね。たいていは突然のことに動揺し、絶望してやってきます」
上司から「なぜ“敗戦処理”をするのか」聞かれた
患者の死と家族に向き合って16年。聞けば、新城氏が行っている日々の診療内容は、まさに穏やかでゆるやかな人生会議そのものだった。緩和ケア医が行う患者主体の人生会議、それはいったいどのようなものなのか。
新城氏自身は、20代で病院の内科医として勤めていた頃から、末期がんの患者を進んで担当していた。30歳でホスピスの専門医になろうと決めたとき、上司からは「なぜ、まだ若いのに“敗戦処理”のような仕事をするんだ」と止められた。

「敗戦処理のイメージは言い得ていると思いました。通常、医師は患者を治そうと治療・診察をしています。その人が亡くなっていく姿を見るのはパワーがいるし、つらいことです。家族が『先生を信じていたのに治してくれなかった』と恨みを抱くこともある。
だから、もう手を尽くしても治りようがないなら、死に向かって伴走する緩和ケア医にバトンタッチできたほうがいい。患者にとっても家族にとっても、主治医にとってもです。僕はあえて、そういう場を専門とする医師になろうと決めたんです」
総合病院のホスピス病棟に勤め始めた新城先生が、治療中の患者の入院部屋に診察に行くと、「あの先生が来たからには、もう長くない。上の階のホスピス病棟に行くことになるんだ。そして最期はもっと上(天国)に昇るんだ」と患者たちはうわさをしたという。



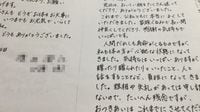



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら