「緩和ケア医が来たら、嫌な話をするとみんなわかっていますからね。僕の存在が死を彷彿とさせる。坊さんのような存在です(笑)。だから逆に話しやすい。患者さんやご家族も僕に向き合うときは、『最期が近い』と覚悟をしたうえで、身構えて話をしてくれる。それはある意味気持ちが切り替えられているということです。その土台がないと、緩和ケアについて、終末医療についての話など、なかなかできませんから」
ホスピス病棟や自身が経営するクリニックで、患者や家族と初めて向き合うとき、新城氏が心がけているのは、まず「自分を好きになってもらうこと」だ。
「最初の診療では、まずは相手の話をひたすら聞くことに徹します。暗い雰囲気にならないよう、努めて明るく苦労や心配を聞きますね。『突然余命3カ月と言われて絶望した』とおっしゃれば、『それはショックでしたねぇ』とただ受け止める」
延命するかしないかを問うようなことはしない
病院での話し合いの場では、医療者側が多く話し、患者や家族は聞くだけという構図ができるものだ。質問をするとしてもせいぜい1つか2つ。だが、新城氏のように、『あなたの言うことを全部聞いていますよ』という姿勢を見せる医師の前で、患者は少しずつ心を開いていく。
また、本質的には延命という治療も存在しない、もはや限られた命とわかっている相手に、 “延命するかしないか”を問うようなことは決してしないと新城氏は言う。
「『延命しますか? しませんか?』と問えば、家族は『延命しないでくれ』とは言えませんよね。逆に本人は、たとえ『あらゆる手を尽くして延命してほしい』と思っていても言えない無言の圧力を感じるでしょう。そんなことを医療者が事前に聞くのはあまり意味がないことのように思います」
避けられない死を認めたうえで、患者自身がどう過ごしていくかを考える。そのために新城氏は多くの時間を割くという。日をあけずに繰り返し話し合いの場を設けると、3、4回目くらいの診療で、自分自身のことを語り始める患者は少なくない。



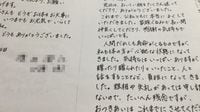



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら