子ども時代に周囲の助けを得られなかった有紀さんは、その後大人になって、自ら助けを探し求めてきました。さまざまな場に足を運びましたが、なかでも「救われた」と感じたのは「宗派を超えたお坊さんたちがボランティアで運営している自死遺族のための法要」だったそう(自死・自殺に向き合う僧侶の会)。
自ら助けを探し求めて
「自死ということを隠さずに法要ができる。それだけで、私は結構救われました。実際の親族の法要は『お父さんはいい人だった』みたいなことしか言わないわけですよ。死ぬまで頑張って生きてきたことは、ほかの死因の人たちと変わりないのに、自殺というだけで生前の歴史が何も語られないっていうことに、気持ち悪さがあって。この法要は、自死に特化した場であることが私にとってはすごく安心でした」
また、自分の経験や思いを話したり書いたりして表に出してきたことも、大きな救いになったと言います。
「32歳ごろから1年間、カウンセリングに通ったのですが、最初はすごく抵抗がありました。そもそも私が悪いわけではないのに、なぜ自分で高いお金を払って?と思って。でも通ってみたら、カウンセリングで怒りを出すことができ、すごく助けになったと感じます。いまは比較的安いオンラインのカウンセリングサービスもあるので、いろんな人におすすめしたいです。
書くこともおすすめです。焦らないで自分のペースでできるし、相手の反応を気にしなくて済むので。私もそうでしたが、傷ついている人ってこれ以上傷つきたくないから、話すときはすごく緊張するんですよ。私は『親への出さない手紙』みたいなサイトにひたすら書いて、ちょっとすっきりしました。基本書きっぱなしの場なんですが、私が『死にたい、死にたい』って書いていたら、『ちゃんと見ている人もいるし、お父さんはあなたのことを愛しているからちゃんと生きてね』と返事を書いてくれた人がいて。『なんだ、身内よりも外の人のほうがやさしいな』って思いました」
今でもたまに調子が悪くなるときはあるものの、一時期ほど死ばかりを考えることはなくなったといいます。
取材から1カ月ほど経った頃、有紀さんから再び、連絡をもらいました。たまたま知り合った相手に精神疾患があったことがわかり、これをきっかけに、昔の母親の気持ちが想像できるようになったそう。
「妄想や躁うつがあり、性的欲求が暴走した父と一緒に暮らすのが、どれだけ母にとって負担だったことか。親族みんなに反対されるなか職につくのが、義父母と顔を合わせながら毎年墓参りに行くことが、どれだけきつかったか。
いま想像できるのは、まったくもって迷惑で、思い出したくもないほど苦痛だったのだろうけれど、母は父のことを愛しているし、私のことも愛している、ということです。
家族であっても立場によって見えるものは違うので、つらさを分かち合うことは愛があっても難しい。とくに精神疾患が関係する場合は、患者とかかわったことがないと、その大変さを実感、想像することはできないんだと感じます」
父親の死から四半世紀を経て気づいた事実。これからもまだ、そんな発見はあるのかもしれません。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら




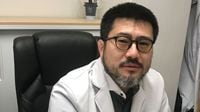




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら