両親が別居して母親の実家に身を寄せたのが小4の冬。父親は入退院を繰り返すようになっていました。この頃の記憶は定かでないのですが、父方の祖父母がときどきやってきて「明らかに母親を責めている」ということは、子どもながらにもわかりました。
父方の祖父母からはたびたび「お父さんとお母さん、どっちが好き?」と聞かれ、「ザラザラとした気持ち」を感じたそう。どっちも好きにきまっているのに、なぜそんなことを聞くのか? 祖父母はどうやら、母親が専業主婦をやめて働き始めたために、地方出身のエリートだった息子がおかしくなってしまった、と信じているようでした。
ある夜、母親から「お父さんが病院に行ったから」と言われ、有紀さんは病院へ連れて行かれます。そのときはわかりませんでしたが、父親が自殺を図ったのです。なんとか一命を取り留めますが、脳死状態が続いた末、結局は亡くなってしまいました。入院期間が2、3日だったのか、数週間だったのかは覚えていません。有紀さんが小学5年か6年の冬のことです。
「なんで死んだの?って、母親にいちおう聞きました。そうしたら『心不全』とか言われて。『そんなわけない』と思いながらも、それ以上はこわくて聞けなかった。でも『おかしい』というのはすごく感じるんですね。子どもって、大人が思うよりもずっと言語外のことを感じるから、大人が何かを隠していることだけはよくわかる。
すると呪いがかかるんです。1つは『聞いちゃいけない』、もう1つは『自分がそのことについてどう感じているかをしゃべってはいけない』という、2つの呪いです」
父親が死んだ理由もわからず、自分の本当の気持ちも隠さなければいけない。それは「生殺しの地獄」であり、「死ぬほど苦しいこと」でもあったといいます。
見過ごされた子どもの痛み
「子どもに事実を隠すことは、本当にやってほしくないです。子どもって自分を全能だと思っているから、その裏返しで、悪いことがあったら自分のせいだと思う。『私が何か悪いことをしたから、お父さんは死んだのかな』とか。実際は何の因果関係もないのに。あのときの私には、『お父さんはこういう病気にかかっていて、だから不幸にして彼は死を選んだけれど、それは決してあなたのせいではないんだよ』という説明が必要でした。
『あなたのためを思って言わなかった』と言うけれど、大人が子どもの感情の揺れに付き合えなかっただけ。でも本来は、子どもでも大人でも感じたことをちゃんと吐き出せる場所があって、『あなたがそう感じることは当然だと思うよ』と、否定されずに受け止めてもらえる場所がほしかった。それがなかったから、私はものすごく苦しかったんです」
父親が亡くなってから2、3年後、中学生だった有紀さんは、たまたま見た母親の定期入れに「知らないおじさんの写真」を見つけます。恋人だろうと察しながら、尋ねることはできませんでした。




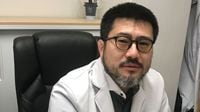




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら